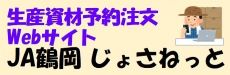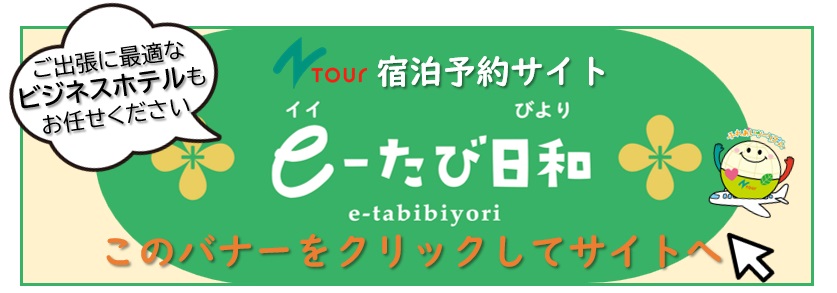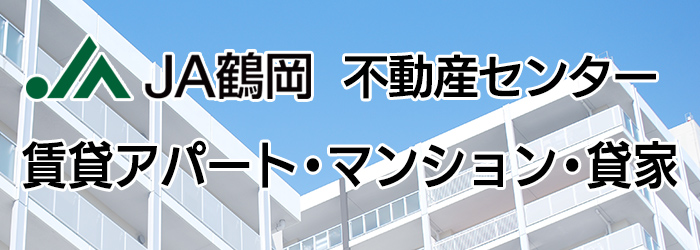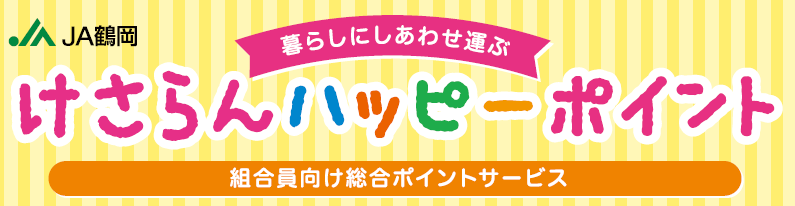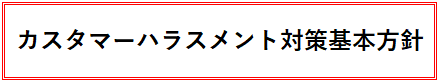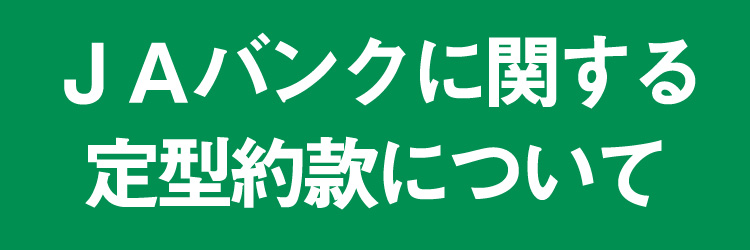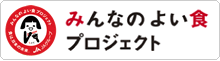ドキュメンタリー映画「弁当の日」を上映/第2回あぐりセミナー
JA鶴岡は9月3日、鶴岡市農村センターで第3回JAあぐりセミナーを開いた。組合員や親子連れ、食に関わる仕事に就く市民ら89人が参加。食育の大切さを伝えようと、映画「弁当の日『めんどくさい』は幸せへの近道」を上映した。
「大人は決して手伝わないで」というルールの下、子ども自らが台所に立ち、自分の弁当を作る食育活動を題材にしたドキュメンタリー作品。「食事作りは親の役割」という社会環境で育った子どもたちが、「自分で作る」チャンスを得たとき、本人や家族の中に芽生える成長や気付きを、笑いや涙を交えて描いた作品だ。
「JAの時間」では、職員がJAの事業や理念、地域貢献活動などを紹介した。
参加した50代の女性は「食は生きていくためにはとても大切なこと。体のためだけでなく、心も一緒に作り上げていくと感じた。子どもたちとも、もっと一緒に食について楽しく学んでいきたい」と話した。

「弁当の日」を鑑賞する参加者

映画を通して子どもへの食育の大切さを学んだ


園児らが❝さやもぎ❞体験
JA鶴岡青年部上郷支部は8月25日、鶴岡市上郷コミュニティーセンターで上郷保育園の園児と管内特産のエダマメ「だだちゃ豆」の収穫体験を行った。
子どもたちに作物を育てる楽しさを知ってもらいたいと、5月に同園の園児らと一緒に「だだちゃ豆」の苗を定植。自分で育てた作物が生長する様子を、散歩の時などに見てもらい、食農教育につなげており、日々の管理は青年部員が行ってきた。
例年は五十嵐亮支部長の圃場(ほじょう)で収穫体験を行っていたが、今年はさやもぎ作業を体験。五十嵐支部長から収穫のこつを教わった後、年少から年長までの園児29人が、それぞれ「だだちゃ豆」の株を持ち、自分の手でひとつひとつさやをもぎ取った。
収穫を体験した児童は「だだちゃ豆が大好きなのでとても楽しかった。早く食べたい」と笑顔を見せた。
収穫した「だだちゃ豆」は、おやつとして提供されたほか、園児らが自分たちの手でさやもぎをした「だだちゃ豆」を持ち帰り、家族と一緒に味わった。

園児と一緒に収穫を楽しむ青年部員
特産「だだちゃ豆」専用自動販売機が登場
JA鶴岡は特産「だだちゃ豆」を一年中おいしく味わってもらおうと、鶴岡市にあるJA直売所「もんとあ~る白山店」の入り口前に「冷凍殿様のだだちゃ豆」自動販売機を設置し、8月29日から販売を開始した。茹でた枝豆を急速冷凍していて、自然解凍や流水解凍して味わうことができる。24時間、365日稼働し、年間のべ50万人の来店客に特産物を広くPRする。
商品は人気品種の「白山」「尾浦」のほか、「甘露」「早生白山」を混ぜた「ミックス」の3種類を用意。価格はいずれも1個400㌘、800円(税込み)で、味付け用の塩も添付している。遠方へのお持ち帰りや土産用として保冷バッグも同自販機で販売している。
庄内藩の殿様の発言にルーツを持つ「だだちゃ豆」。同JA産直課ではJA鶴岡創立50周年と酒井家庄内入部400年を記念し、全国でも類を見ない枝豆専用の自販機設置を企画した。商品名は「冷凍殿様のだだちゃ豆」として販売。自販機の両サイドには酒井家の家紋や「だだちゃ豆」の由来などがラッピングされている。
同課の鈴木大亮係長は「とれたてのおいしさを一年中、気軽に楽しんでいただくことで、「だだちゃ豆」が持つ魅力をもっと広げていきたい」と話した。
.jpg)



良質米協議会作柄検討会を開催
JA鶴岡、鶴岡市で組織される鶴岡地域良質米生産推進協議会は8月29日、水稲作柄調査検討会を開き、関係者約35人が参加して稲の生育状況や刈り取り適期を確認した。
「はえぬき」、県産米「雪若丸」・「つや姫」の管内3カ所の展示圃を巡回。耕種指導係が青籾歩合などを調査し、各圃場で取り組んでいる目的や栽培技術の内容を説明した。
管内では出穂は平年より3日程度早いが、出穂後の日照不足などにより登熟進度が緩慢で刈り取り適期の判断が難しい状況。生産振興課は積算気温を目安にしながらも登熟状況や青籾歩合・籾水分、圃場の状況などを確認して適期内に刈り取りを行うよう呼び掛けた。
伊藤淳専務は「管内では幸いにも大きな災害もなく作況はほぼ平年並み。生産者には安全作業で良品質・全量1等米となるよう努めてほしい。米価については1円でも高くなるよう期待に応えたい」とあいさつを述べた。


親子でだだちゃ豆収穫体験 第2回あぐりスクール
JA鶴岡は8月20日、鶴岡市内で第2回あぐりスクールを開き、市内の小学4~6年生の親子11組22人が参加した。
はじめに大泉地区の農家77戸で構成される農事組合法人大泉フェローズの圃場(ほじょう)でエダマメ「だだちゃ豆」の収穫を体験。同法人の役員らから収穫のコツを教わった後、子どもの背丈ほどの高さに育った主力品種の「白山」を親子で力を合わせ、根元から力いっぱい引き抜いていた。参加した児童は「根っこを引き抜くのにとても力が必要で難しかったが、楽しかった」と笑顔を見せた。
その後、田川コミュニティーセンターに移動し、一般社団法人田川そばの郷のメンバーが講師となり、 田川地区で生産されたソバ「でわかおり」を使ったソバ打ちに挑戦。講師が粉と水を混ぜ込む水回しや練り、生地を薄く伸ばすのしやソバの切り方など一連の作業を実演して見せた後、家族ごとにソバ粉と小麦粉を混ぜ合わせたものに水を加え、風味が飛ばないようすばやく混ぜ合わせて作業した。生地がまとまったら、薄く伸ばし、小間板とソバ切り包丁を使って自分好みの太さの麺にしていた。
その他に「この本だいすきの会」庄内支部のメンバーによる読み聞かせも行われ、充実した時間を過ごした。
参加した児童は「だだちゃ豆の根っこがしっかりしていて収穫するのも、自分の手でさやもぎをするのも大変だったけど楽しかった」と笑顔を見せた。
保護者からは「だだちゃ豆の収穫もそば打ちも初めての体験だったので、親子そろって良い経験になった」との感想が聞かれた。
第3回あぐりスクールは、10月下旬に赤かぶの収穫体験と魚のさばき方講座の開催を予定している。

親子で協力して収穫しました!

そば打ち体験を楽しむ親子

ご参加いただきありがとうございました!
BISTRO下水道研究発表会in鶴岡
下水道資源を農作物の栽培等に有効利用し、農業等の生産性向上に貢献する取組「BISTRO(ビストロ)下水道」の研究発表会が8月23日、鶴岡市の山形大学農学部で開催された。
研究発表では処理水を利用した飼料用米栽培、処理過程で発生する消火ガス発電の余熱を利用したハウス加温による野菜の栽培などの取り組みを同農学部や関係機関が報告した。
鶴岡市では市、山形大学、JA鶴岡など6者が産学官連携でビストロ下水道に取り組んでいる。JA鶴岡は2016年に市からコンポストセンターの運営と販売を受託。同センターでは浄化処理した下水汚泥を堆肥に変え供給している。
パネルディスカッションでは、関係機関を代表した5人がパネラーとして参加し、JA鶴岡からは営農販売部生産振興課の今野大介課長が参加した。
JAの立場からビストロ下水道を生産者や消費者に普及させていくためにはという討議では、今野課長が「同センターは1986年から稼働し35年ほど経過している。管内では特別な資材ではなく、堆肥と同じように利用していて、生産者にも広く普及している」と述べた。
また「資源循環では管内CE(カントリーエレベーター)で生じたもみ殻をコンポストに利用している」と述べ「農水省ではビストロを「みどりの食料システム戦略」や肥料高騰等に対応する化学肥料削減のための対策のひとつとして示している。消費者にも理解を示す機会となっている」と訴えた。

意見を述べる今野課長(パネル中央)

「田川焼畑赤かぶ」伝統の山焼き
JA鶴岡田川焼畑赤かぶ専門班は8月22日、班員13人が参加して田川地区の杉伐採地で恒例の山焼きを約85㌃行った。
山焼きは同地区特産の赤カブ「田川焼畑赤かぶ」生産にかかせない伝統的自然農法。土壌改良や防除効果がある焼畑農法にこだわり毎年8月の炎天下に行われる。
杉枝の天地返し、下草刈り、延焼防止などの事前作業を終えた山の斜面上側から火をつけて焼く。炎熱の中、急な傾斜で燃え広がりを調整しながらの過酷な作業だ。杉の葉と枝の灰が肥料となり、山肌に元肥を散布して播種する。
特産「田川焼畑赤かぶ」は10月上旬に収穫を迎え、パリッとした食感で辛味があるのが特徴だ。主に地元の漬物業者へ出荷され、出荷数量は約5.5㌧を見込む。
長谷川則子班長は「毎年、大変な作業を経て生まれる「田川焼畑赤かぶ」は格別なものだと思っている。多くの方に食べていただきたい」と話した。





青年部大泉支部が田川保育園にだだちゃ豆をプレゼント
JA鶴岡青年部大泉支部は8月18日、鶴岡市の田川保育園に特産のエダマメ「だだちゃ豆」をプレゼントした。「だだちゃ豆」はおやつで提供される。
「だだちゃ豆」のかぶり物をかぶった松浦雄太支部長が「おいしい「だだちゃ豆」を頑張って作ったので、みんなで食べて」と話し、袋詰めした「白山」5㌔を園児に手渡した。
「だだちゃ豆」を受け取った児童は「だだちゃ豆が大好きなので早く食べたい」と話した。
伊藤直樹園長は「この「だだちゃ豆」は農家さんが頑張って作ってくれたもの。食べるときは1粒1粒に感謝の気持ちをもって味わってほしい」と呼び掛けた。
同支部では部員の多くがエダマメを栽培。「だだちゃ豆」を食べて夏を元気に過ごしてもらい、地域農業への関心を高めてもらおうと毎年、市内の保育園などに贈っており、今年で18回目。

園児に「だだちゃ豆」をプレゼントする松浦支部長㊧
金融本店「夏のご来店感謝デー」を開く
JA鶴岡金融本店は8月15日、夏のご来店感謝デーを開いた。
職員はこの日のために新調したおそろいのTシャツ姿で出迎え、定期貯金や各種取引、相談をした方にはマグカップやジュースが進呈されたほか、JAバンクアプリや共済Webマイページ利用者にカキ氷がふるまわれた。
もんとあ~る駅前店お盆セールにあわせ、JAバンクキャラクター「よりぞう」も登場。来店者とふれあってイベントを盛り上げた。
金融本店の後藤真紀子課長は「コロナ禍でまだまだイベント開催は難しいが、JAカードやネットバンクなど、魅力的な商品がたくさんあることをPRできれば、と思い企画した。これを機にJAファン拡大につなげていきたい」と話した。

JAバンクアプリ利用者などにかき氷がふるまわれ、よりぞうもイベントを盛り上げた。
新型コロナウィルス感染症拡大に伴う 窓口営業時間の変更について
_20220901-1024x1462.jpg)