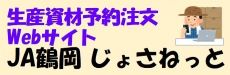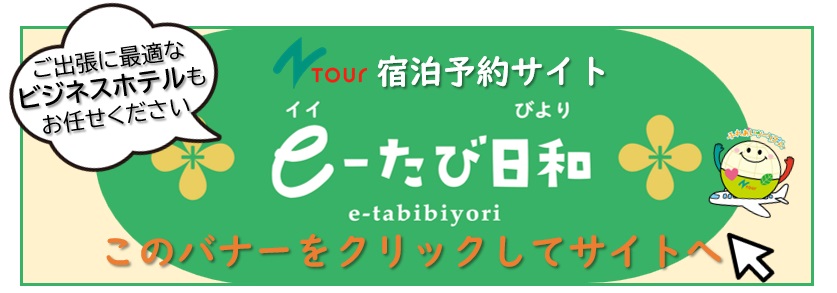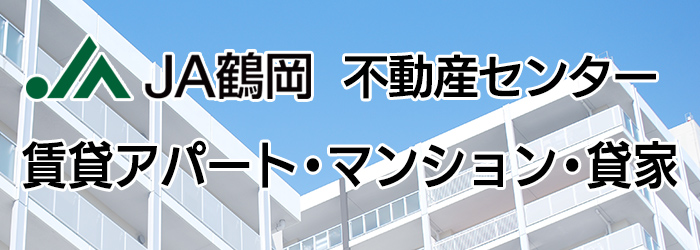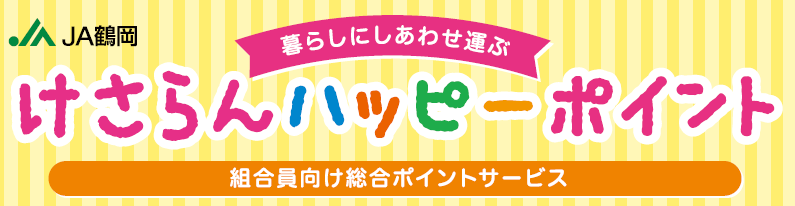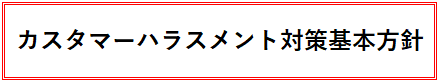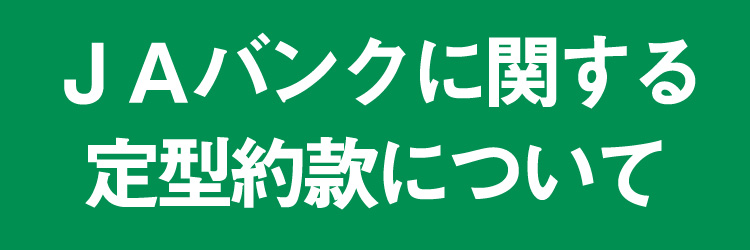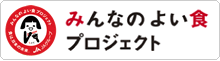ミニトマト栽培基礎講習会を開く
生産振興課は8月3日、京田地区にある生産者の圃場(ほじょう)でミニトマト栽培基礎講習会を開いた。同講習会は生産拡大に向けてミニトマト専門部と連携し、新規生産者や栽培年数が浅い人、生産を予定している人を対象としている。
園芸指導係が今後の栽培管理について説明。大雨などにより畝間に水がたまった場合は排水をしっかり行うことや、潅水は少量多回数で行うよう呼び掛けた。樹勢に応じた追肥の施用間隔や、有効な遮光資材の活用方法について説明した。
参加した生産者は園芸指導係に質問しながら今後の栽培管理について学んだ。


市民が鶴岡産の花でフラワーアレンジメント体験/3年ぶり第1回あぐりセミナー
JA鶴岡は7月29日、鶴岡市農村センターで3年ぶりに第1回JAあぐりセミナーを開き、 市民ら24人が参加した。市内で「花蔵」を営む三浦淳志さんを講師に、鶴岡産の花を使ってフラワーアレンジメントを楽しんだ。
同JA花き振興部会が生産した同市産の白、ピンク、緑、黄色のトルコギキョウのほか、モカラなど6種類の花を使用。参加者は色とりどりの花を花器にいけ、配置のバランスを考えながら、彩豊かな作品を仕上げた。参加者は「トルコギキョウをたっぷり使い、とても楽しくアレンジメントを作ることができた」と話した。
「JAの時間」では、花き振興部会の取り組みや、管内で生産している花の特徴、花の栽培から出荷までの流れなどを紹介した。花の生産者に聞いた花の魅力、楽しむ方法などを特集した市民向け広報誌『ぱさらん』も配布した。

三浦さん㊧から花の説明を聞く参加者

三浦さん㊨の指導で鶴岡産のトルコギキョウを使って作品を仕上げる参加者
もんとあ~る4周年祭でにぎわう
JA鶴岡のファーマーズマーケット「もんとあ~る」は7月23、24の両日、3店舗で2018年の店舗名称「もんとあ~る」へのリニューアルオープンを記念した「4周年祭」を開いた。
開店前から新鮮な農産物を買い求めようと地元住民らの列ができ、周年祭期間中の「もんとあ~る」3店舗の来場者数は約4500人。多くの買い物客でにぎわい、約1100万円を売り上げた。
期間中は、2000円以上の購入で産直卵のプレゼントやポイント10倍などの3店舗共通企画のほか、白山店では全国より8つの提携JAよりモモやスイカ、マンゴーなど各地の特産品が店頭に並んだ。その他にも、JA鶴岡オリジナルブランド「鶴姫メロン」「鶴姫レッドメロン」の限定特価販売や庄内砂丘メロンが全国一律500円で発送できるといった限定特価で販売された。
また、今年はJA鶴岡50周年記念イベントとして、先着600人へ「紅白まんじゅう」のプレゼントや、さまざまな景品が当たる「くじ引き」を行い、おおにぎわいをみせた。
この日を待ちわびた来場者に次々と購入された。
JA営農販売部産直課の高橋千津課長は「今年も多くのお客さまにご来店いただき、盛大に4周年を迎えることができた。これからも買い物を楽しんでもらえるよう心がけていきたい」と話した。

8つの提携JAが各地の特産品を限定販売

提携JAの特産品がずらり

もんとあ~る4周年祭で多くの方が買い物を楽しんだ
「だだちゃ豆」初出荷式を開く
JA鶴岡は7月25日、鶴岡市のJA北部集出荷場で特産エダマメ「だだちゃ豆」の初出荷式を開いた。関係者約40人が出席し安全祈願祭の後、JA代表者らがテープカットをして関東の市場に向けて「早生甘露」を積んだトラックが出発した。
佐藤茂一組合長は「消費者の期待に応えることができる「だだちゃ豆」ができた。栽培面積は昨年よりも増え、全国のファンにたくさん届けることができる」と述べた。
さらに「今年はJA鶴岡合併50年。商品名「殿様のだだちゃ豆」として使用している酒井家も庄内入部400年の記念の年にあたる。例年以上に商品名を前面に出して販売していく」と述べた。
加賀山雄専門部長は「心を込めて作った「だだちゃ豆」を広く皆さんに食べてほしい。これから暑さが増していくのでぜひビールのお供に」と話した。
生育は順調で、品質・収量ともに概ね平年並み。安全安心で日本一おいしい「殿様のだだちゃ豆」を全国に届ける。出荷は7月下旬から開始し、8月中旬をピークに9月上旬まで続く。




「だだちゃ豆」直売開始 / 女性部大泉枝豆直売グループ
鶴岡市のJA鶴岡大泉支所駐車場内に22日、特産エダマメ「だだちゃ豆」の直売所がオープンした。JA鶴岡女性部大泉支部の大泉枝豆直売グループの15人が出荷し、8月末ごろまで毎日開く。
開設43年目の今年も、新型コロナウイルス感染防止のため、試食は取りやめ、営業時間も午前8時30分から正午までに短縮。また、マスク着用や手指消毒の他、飛沫(ひまつ)感染を防ぐシールドを設置。行列を避けるため、番号札を置いて案内するなどの対策も行う。
今年は、6月上旬の降ひょうとその後の降雨、強風の影響で生育遅れがみられたが、おおむね平年並みに生育は回復。同グループの松浦美保会長は「みなさんにおいしいだだちゃ豆を食べてほしいと会員が丹精込めて栽培しているので、一粒一粒味わって食べてほしい」と話す。
直売は、早生品種「小真木」の枝付き(1㌔束)と袋詰め(600㌘入り)を皮切りに、8月初旬からは「早生甘露」、8月上旬から「甘露」、8月中旬から「早生白山」、8月18日ごろから「白山」の品種へと続く。肥料や資材費の高騰を受け、販売価格を50円値上げし、850円とした。

感染防止対策を徹底して運営する「だだちゃ豆」直売所
「だだちゃ豆」生産者大会を開く
JA鶴岡だだちゃ豆専門部は7月21日、鶴岡市のJA北部集出荷場で「だだちゃ豆」生産者大会を開いた。生産者や関係者が参加し、安全安心で日本一おいしい「だだちゃ豆」を消費者に届ける事を確認した。
今年の生育は順調で品質・収量ともに概ね平年並み。出荷は7月下旬から始まり8月中旬に最盛期を迎え、9月中旬までを見込む。
加賀山雄専門部長は「いよいよ出荷が始まる。「だだちゃ豆」の名声をもう1段上げたい。皆さんからさらなる協力をお願いしたい」と呼び掛けた。
佐藤茂一組合長は「栽培面積は昨年よりも増加している。栽培の機械化も進んでいるし、JAの共選施設も要望があれば稼働拡大を検討するので、面積拡大に努めてほしい。暑い日が続くが体調管理には十分に気を付けてほしい」と呼び掛けた。
「だだちゃ豆」を広く知ってもらうため、横浜駅構内にビッグポスターや東横・京急線の車両内にポスターを期間限定で掲示する。8月8日の「だだちゃ豆の日」に向けて、2日から加茂水族館や庄内空港にのぼり旗などによるPRを予定している。

あいさつを述べる加賀山専門部長

あいさつを述べる佐藤組合長

協議事項の説明を受ける生産者
女性部西郷支部が旬の農産物を寄贈
JA鶴岡女性部西郷支部は7月20日、鶴岡市内の特別養護老人ホームしおん荘、養護老人ホーム思恩園、児童養護施設・七窪思恩園に、取れたての夏野菜や特産のメロンをプレゼントした。
「メロン一粒運動」は、1976年から西郷婦人会が社会福祉への貢献を目的に始め、2014年から女性部西郷支部と合同で取り組んでいた。2021年度をもって西郷婦人会が解散したことから、女性部が活動を引き継ぎ、同支部の部員の家庭で収穫した農産物を寄贈することとした。今年もメロンやカボチャ、キュウリ、ナスなど西郷産の旬の農産物が集まった。
七窪思恩園では、女性部員らが玄関前で出迎えた職員に農産物を手渡した。
小笠原せつ支部長は「西郷地区で育てたおいしいメロンと野菜を食べて、これからも元気に過ごしてほしい」と話した。
寄贈された農産物は、施設の食事として利用者に提供される。

部員の愛情がいっぱい詰まった農産物をめしあがれ!

旬の農産物を食べて元気に過ごしてください!
地元の小学生がメロン畑や選果場を見学
JA鶴岡西郷支所は7月20日、鶴岡市立上郷小学校の校外学習を受け入れ、同校3年生15人に特産のメロンについて特徴などを伝えた。
同支所では毎年6月から7月にかけて、鶴岡市内の小・中学校の校外学習に講師として協力。今年は9校、約400人を受け入れた。
庄内砂丘にあるメロンの圃場(ほじょう)では、JA職員が管内のメロンの栽培面積や栽培期間、砂丘地で栽培する理由などを説明。
JA西郷選果場では、箱詰めされたメロンがローラーコンベヤーに運ばれて出荷される工程を見学。児童は、管内では「アンデス」「鶴姫」「鶴姫レッド」の3品種を栽培し、年間55万㌜(1㌜5㌔)を出荷していることなどの説明を受けた。児童からは「メロンの栽培で大変なことは何か」「一日に何個収穫するか」など多くの質問が出された。見学後、児童は「お米を作るときは機械を使うのに、メロンは機械を使わずに作らなければならないことを知って驚いた」と話した。

選果場でメロンの規格について説明するJA職員

メロンの圃場を見学する児童
青年部員が収穫した野菜を使って子どもたちと「収穫感謝祭」

分担してカットしたサラダを盛り付け

ご飯の上に素揚げにした野菜をトッピング

夏野菜カレー&サラダが完成!
大泉枝豆直売グループ圃場巡回と全体会議を開く
JA鶴岡女性部大泉支部の大泉枝豆直売グループは7月8日、特産エダマメ「だだちゃ豆」の圃場(ほじょう)巡回と全体会議を開いた。会員14人が参加し、防除対策の徹底を確認した。
市内の圃場2カ所で「小真木」や「早生甘露」などの丈や葉数を調査。春先の低温の影響で生育遅れがみられたが、おおむね平年並みに生育は回復した。ハムシ、ヨトウムシによる葉の食害が散見され、JAの園芸指導係が病害虫防除の薬剤や散布時期、使用回数などを指導し、防除の徹底を呼び掛けた。
JA大泉支所で行われた全体会議では、直売所では開店前から密集が予想されるとし、営業時間短縮やグループ員の店番制の廃止、飛まつ感染防止シールドの設置、行列を避けるため番号札を設置して順番に案内するなど、新型コロナウイルスの感染拡大防止策の徹底を確認した。
グループの生産者は15人。直売所は7月下旬から8月末頃までJA大泉支所駐車場内の特設テントで営業する他、インターネット販売でも対応する。

「だだちゃ豆」の生育状況を確認する会員と園芸指導係

直売所の運営について確認した