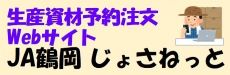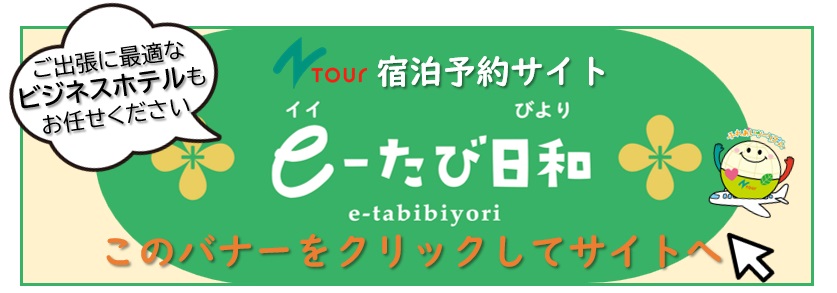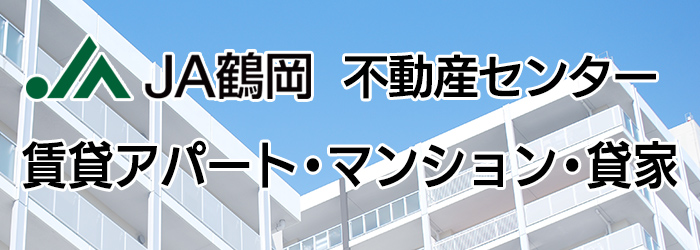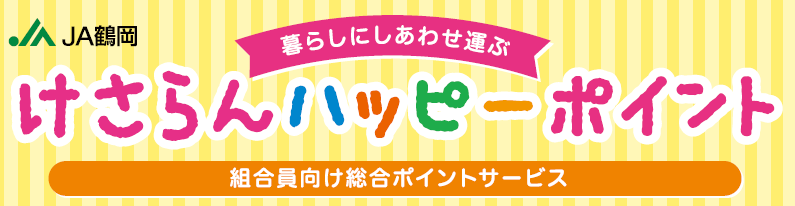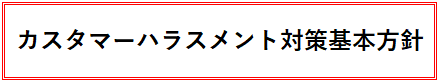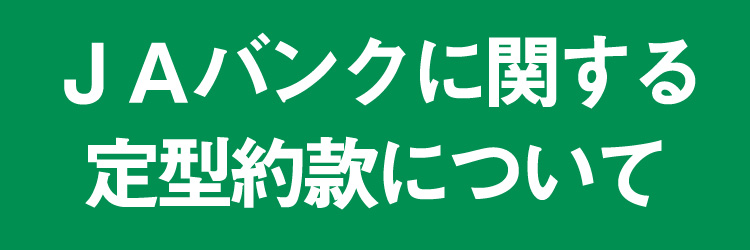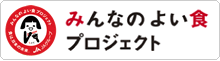シャインマスカット現地研修会を開く
県庄内総合支庁農業技術普及課産地研究室は7月16日、ブドウ「シャインマスカット」現地研修会を酒田市浜中にある同研究室の試験圃場(ほじょう)で開いた。
生産者、県庄内総合支庁農業技術普及課、JA鶴岡、JA庄内たがわの関係職員約30人が参加し、試験栽培しているシャインマスカットの現在の生育状況や栽培のポイントなどを県担当職員らが説明した。
これからの栽培管理について県の担当者は、房形の輪郭を整える仕上げ摘粒(てきりゅう)では、房の上段・中段・下段それぞれの箇所で残す果粒、取り除く果粒の数や向きを説明し、注意点として「ハサミでする作業になるので、少しでも粒に傷をつけると、そこから腐敗したりして商品性が落ちるので気を付けて作業してほしい」と呼び掛けた。新梢(しんしょう)管理では、収穫期1カ月前の8月頃、摘心(てきしん)することで糖度の上昇、新梢の登熟を促進する効果があると説明した。袋かけでは、果房を被覆することで病害虫被害を防止し果粉がのった高級感のある果実に仕上がると説明し、袋は白色に比べ緑、青の色付袋は収穫期を遅くできるが、被覆が早すぎると糖度が上昇しにくくなると注意を呼び掛けた。
-1-500x333.jpg)
栽培のポイントを説明する県普及課職員(7月16日、山形県酒田市で)
エダマメ「おつな姫」目揃い会を開く
JA鶴岡は7月13日、鶴岡市のJA北部集荷場で生産者約60人が参加して早生エダマメ「おつな姫」の目揃い会を開いた。
JAの販売係は「昨年以上に企画販売を拡充した。しっかり販売していくので1袋でも多く出荷してほしい」と呼び掛けた。
JAの園芸指導主任がサンプルを示し、規格を確認した。A品に格付けできるのは品質・形状・色沢が良好で、病害虫のない1さや2粒以上の適熟なものと説明。降雨と曇天の影響でやや生育が鈍化している。鮮度保持のため調製から出荷までの温度管理や、荷姿では量目不足に注意してほしいと呼び掛けた。
「おつな姫」は、茶豆のような独特な香りと、かむほどに深みを増す甘さが特徴。管内では88人が栽培し、7月末までに昨年並みの45㌧の出荷を予定。23~25日ごろに最盛期を迎える見通しだ。

サンプルを見ながら「おつな姫」の出荷規格を確認する生産者
大泉枝豆直売グループ圃場巡回と全体会議を開く
JA鶴岡女性部大泉支部の大泉枝豆直売グループは7月10日、特産エダマメ「だだちゃ豆」の圃場(ほじょう)巡回と全体会議を開いた。会員14人が参加し、防除対策の徹底を確認した。3カ所で「小真木」や「早生甘露」などの丈や葉数を調査し、JAの園芸指導係が病害虫防除の薬剤や散布時期、使用回数などを指導した。
5月の強風と6月の乾燥の影響もあったが、現在はおおむね平年並みに生育は回復。コガネムシによる葉の食害が散見された。園芸指導係は「梅雨時期が長引き多湿状況にあるため予防防除を徹底してほしい」と呼び掛けた。
全体会議では、直売所の今後の運営について確認した。例年、開店時間前から直売所周辺が県内外からの客でにぎわい、密集状況が予想される。営業時間の短縮やグループ員の店番制の廃止、飛沫防止シールドの設置、行列を避けるため番号札を設置し順番に案内するなど、お客さまと関係者の安全面に配慮した新型コロナウイルスの感染拡大防止対策をとりながら直売所を営業する。
グループの生産者は14人。直売所は7月中旬から8月末頃までJA大泉支所駐車場内の特設テントで営業する他、インターネット販売でも対応する。

「だだちゃ豆」の生育状況を確認する会員と園芸指導係
校外学習で児童が特産の庄内砂丘メロンを学ぶ
JA鶴岡西郷支所は7月3日、鶴岡市立西郷小学校の校外学習に協力し、特産のメロンについて教えた。
同小学校2年生は、生活科の授業の中で5~7人ずつ3班に分かれて地域について学ぶ「町探検」を実施。そのうち1班の5人がJA西郷選果場を見学した。
同選果場では、箱詰めされたメロンがローラーコンベヤーに運ばれて出荷される工程を見てもらい、出荷規格などを説明した。JA園芸指導係が、管内では「アンデス」「鶴姫」「鶴姫レッド」の3品種を栽培し、年間55万㌜(1㌜5㌔)を出荷していることなど説明した。
児童らはメモを取りながら「トラック1台にはメロンが何個入るのか」など多くの質問をしていた。
同支所では毎年6月から7月にかけて小・中学校の校外学習に講師として協力。今年は新型コロナウイルスの影響で、ほとんどの学校の選果場見学が中止となった。

選果場でメロンの品種について説明するJA園芸指導係
稲作展示圃現地研修会を開く
鶴岡地域良質米生産推進協議会は6月26日、稲作展示圃で現地研修会を開き、鶴岡市、生産者、JA鶴岡、県農業技術普及課などの関係者ら約30人が参加した。同協議会は稲作の生産性を高め、良質米生産の確保を図ることにより、農業の発展に寄与することを目的としている。
スマート農業や省力低コストなどの技術の試験導入を行っている3カ所の圃場(ほじょう)を巡回し、担当しているそれぞれのJA耕種指導係が取り組んでいる技術の内容や水稲の生育状況などを説明した。
昨年から試験した開水路向け自動給水機では、スマートフォンでの水温管理や入水止水などについて説明した。4年目となる密播試験では育苗時の施肥と移植後の水管理を説明。試験圃場では比較的風が強く浅植えが難しい圃場ではあるものの茎数が取れている要因としては「育苗時に3回液肥を使用した密播苗にて移植した結果、活着およびその後の生育は良好。活着後の水管理に関しては浅水管理で分げつを促進し、ワキの発生については水交換・田干しを中心に行った。これら一連の管理ができないと茎数確保には至らない」と説明した。
同JAは巡回した各圃場の収量などの数値を検証し、収量増や高品質に向けて今後も技術の普及および拡大に向けて取り組んでいく。
.jpg)
密播の試験圃で取り組み内容や生育状況の説明を聞く参加者(6月26日、山形県鶴岡市山口集落で)
第48回通常総代会を開催
JA鶴岡は6月23日、鶴岡市の東京第一ホテル鶴岡「鳳凰の間」で第48回通常総代会を開いた。
新型コロナウィルスの感染リスク低減を考慮し、総代500人のうち430人が書面による議決権行使、25人が本人出席し、2019年度の剰余金処分案や20~22年度の中期経営計画・第12次地域農業振興運動計画などの11議案を原案通り全て承認した。
佐藤茂一組合長はあいさつで各事業の概況のほか取り組み初年度となる2つの計画について「第12次地域農業振興運動計画では、確固たる100億円産地に向けて運動を展開する。中期経営計画は農林中金が検討している新たな金融店舗システムや高齢化による事業領域の変化を鑑み「持続可能な経営の確立」への事業再構築期間として位置付ける。今後とも事業に対する結集・参画をお願い申しあげる」と述べた。
19年度の事業決算は農業機械の供給高などが好調だったことや農産物の販売数量増にともなう包装資材の供給と施設設備投資が増加したことで購買事業損益は前年比8450万円増。事業総利益は前年比1814万円増の20億8793万円。経常利益は前年比8179万円増で2億6674万円となった。
剰余金処分案では、出資配当金1%などのほか、主食用米などの俵数、青果物、産直品、畜産物の販売額に対して配当する事業分量配当金が提案された。
独立監査人の監査については、19年度から改正農協法の施行にともない、一般公認会計士2人を会計監査人に選任し受監しており、20年度以降も継続する。
総代会に先立ち19年度高品質米生産共励会表彰が行われ、生産組合表彰と個人表彰(品種別表彰)が行われた。

事業概況を述べる佐藤茂一組合長

高品質米生産共励会表彰者の皆さんと佐藤組合長(中央)

書面による議決権行使の呼び掛けにより、本人出席が25人となった第48回通常総代会
上郷支所年金友の会Gゴルフ大会
JA鶴岡上郷支所年金友の会は6月25日、鶴岡市上郷コミュニティーセンターで第14回上郷支所長杯グラウンドゴルフ大会を開いた。会員47人が参加。
鈴木伸明支所長のあいさつに続き、4~6人ずつ10組に分かれ、男女オープンの個人対抗12ホール、2ゲームで腕を競った。
参加者は励まし合い、好プレーが飛び出すと歓声が上がった。
熱戦の結果、大谷の渡部健二さんが優勝。第2位は上京田の佐藤悌一さん、第3位はみずほの佐藤喜代志さんだった。
鈴木支所長は「役員の協力により新型コロナウイルス感染対策を徹底し、無事に大会を開催できた。練習の機会が少なかったにも関わらず、会員のプレー技術は素晴らしかった」と話した。
成績は次の通り。
優 勝 渡部 健二さん(大谷)
第2位 佐藤 悌一さん(上京田)
第3位 佐藤 喜代志さん(みずほ)
第4位 長谷川 幸雄さん(矢引)
第5位 斎藤 昭三郎さん(大谷)
-1.jpg)
ホールポストに狙いを定め、ボールを打つ参加者

上位成績者(左から順に優勝~第5位まで)
民田ナスの目揃い会を開く
JA鶴岡大山園芸振興部会なす班は6月24日、鶴岡市のJA大山支所で在来野菜「民田ナス」の目揃い会を開いた。
JAの園芸指導係がサンプル品を示し、規格を確認した。A品に格付けできるのは品質・形状・色沢が良好で、病虫害・損傷がなく、着色は表面積の6割以上のものと説明。生育は順調で、追肥時期の目安や、病害虫防除など今後の管理についても助言した。
鈴木実班長は「高品質のものを安定出荷できるよう、今後の管理に気をつけてほしい」と呼び掛けた。
「民田ナス」は、鶴岡市で受け継がれてきた在来作物で、昔から地元の人々に親しまれてきた。小粒で、果肉が締まり、歯触りが良く、浅漬けやからし漬けといった漬物が人気だ。同班では、全量を同市の漬物販売会社、株式会社本長に卸している。
株式会社本長の本間光太郎社長は「全国の消費者の方々においしい民田ナスの漬物を届けられるように1キロでも多くの出荷をお願いしたい」と話した。
2019年度は8・8㌧を出荷。20年度は生産者5人が44㌃で栽培し、昨年並みの出荷量を目指す。出荷は10月上旬まで続き、8月に最盛期を迎える。

出荷規格を確認する班員
ミニトマト栽培基礎講習会を開く
JA鶴岡生産振興課は6月24日、鶴岡市で関係者約30人が参加して第2回ミニトマト栽培基礎講習会を開いた。
JAでは、生産拡大に向けてミニトマト専門部と連携し、新規生産者や栽培年数が浅い人、生産を予定している人を対象に、講習会を開いている。基礎的な技術習得や必要な資材など、準備段階から出荷までを学ぶ内容で5回計画している。
2回目となる今回は、5月末と6月中旬に定植した生産者の圃場(ほじょう)で、JAの園芸指導係から栽培マニュアルを使って、資材や施肥などの圃場準備から定植後のかん水や温度管理、整枝などの栽培管理法を学んだ。
参加者からは、かん水チューブの設置方法やかん水のタイミングなどについて質問が出た。
作付け3年目の参加者は「講習会は作業前に要点を確認できるので助かっている。今年は昨年の課題を生かして栽培したい」と意気込んだ。

ミニトマトの栽培管理法を学ぶ参加者
大玉トマト目揃い会を開く
大玉トマトの本格出荷を前に、JA鶴岡ハウストマト専門部は6月18日、鶴岡市のJA北部集荷場で目揃い会を開いた。
生産者ら16人が参加した。JA園芸指導係が出荷サンプルを見せながら等級別に品質や形状、色合い、果実サイズ、箱詰めの注意点を説明。カラーチャートを示しながら、出荷時は6割着色を基本とし、赤く着色したものはB品とすることを伝えた。参加者は、サンプルを手に取って出荷基準を確かめ、選別を徹底、統一することを確認した。
販売担当者は「昨年は集荷数量がピークを迎えた頃に買い控えが起き販売に苦戦した。課題を生かし、今年は新たな市場へ出荷することで販売先を増やし、事前に値決めをして販売するなどで販売単価をキープしていきたい。鶴岡の品質は良いものだとアピールしてしっかり販売していくので、選別を徹底して出荷に協力してほしい」と呼び掛けた。
専門部ではトマト「桃太郎」と、2019年度より収量や品質面の向上を見込み「りんか409」を栽培。今年は13人が98㌃で栽培する。7月中・下旬に最盛期を迎え、集荷は9月頃まで続く。

大玉トマトの出荷サンプルを確認する生産者