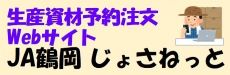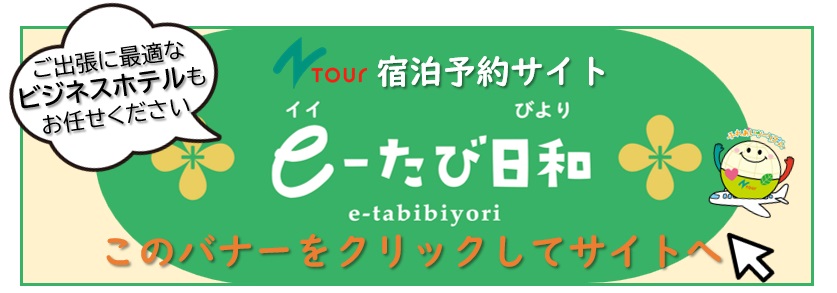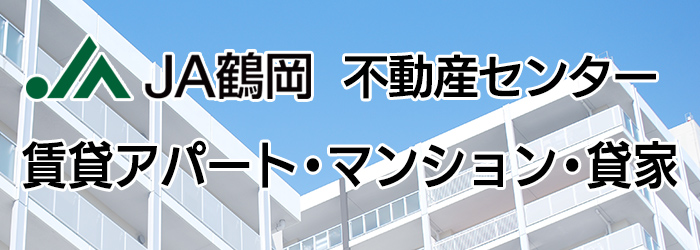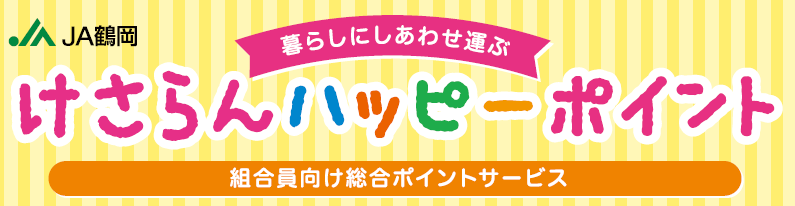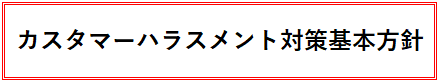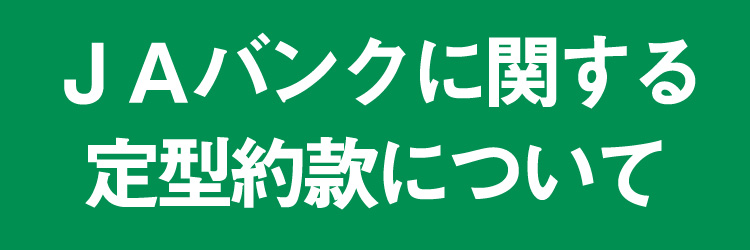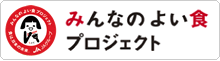乳和食で減塩・あぐりセミナー
JA鶴岡は11月27日、鶴岡市農村センターで第4回JAあぐりセミナーを開き、市民43人が参加した。料理家で管理栄養士の小山浩子さんが「乳和食で減塩&ウェルエイジング・健康寿命百歳を目指して!」と題して講演し、乳和食について理解を深めた。
小山さんは、山形県は食塩摂取量が女性がワースト3位(男性は全国ワースト15位)であることを紹介。高血圧の予防や改善には減塩が必須で、和食に牛乳を使う「乳和食」が有効だとすすめた。
だし汁や水を牛乳に置き換えることで、食塩やしょうゆなどの調味料を減らすことができ、牛乳の旨みとコクが加わることで、おいしい減塩食になり、カルシウムも摂取できる。
参加者は乳清ごはん、かぼちゃのミルクそぼろ煮、塩分半分のみそ汁、温めた牛乳に米酢を加えてできるカッテージチーズを試食した。小山さんは「乳和食はこれからの健康寿命100歳時代を生き抜く新しい考え方の和食。周りの方にも伝えていただき、乳和食でおいしく減塩してほしい」と呼び掛けた。
参加者は「乳和食を初めて知った。牛乳を加えると減塩になり、見た目も違和感なくおいしく食べられることに驚いた。家庭でも実践したい」と話した。
「JAの時間」では、企画管理部総合企画課の菅原正成企画係長が、総合事業と准組合員制度を紹介した。

乳和食を使った減塩について講演する小山さん
にぎわい交流を深めた 北支所組合員交流会
北支所では、組合員交流会を11月22日、東京第一ホテル鶴岡で開いた。管内の組合員・支所職員など約120人が参加。
鶴岡市出身の料理研究家で元吉本芸人の三浦友加氏による講演が行われ、芸人になった理由や占いのアルバイトがきっかけで手相が見られる事から、参加者の性格、恋愛運、健康など手相で占った。思いもよらない性格も分かるとあって参加者同士で手相を見せ合いながら、盛り上がった
交流会では、北支所管内の組合員が栽培した農産物を使った地産地消料理に舌鼓をうち、提供された色とりどりの花は会場を彩った。抽選会も行われ、会場は大いに盛り上がり参加者は交流を深めていた。

三浦氏に手相を見てもらう組合員

管内組合員の農産物を使った地産地消料理が振る舞われた交流会
元気に暮らそう!いきいき教室を開催 けさらん愛、愛サービス
JA鶴岡助けあいの会「けさらん愛、愛サービス」は11月20日、組合員世帯の70歳以上を対象にしたミニデイサービス「元気に暮らそう!いきいき教室」を鶴岡市農村センターで開き、約180人の来場者でにぎわった。
石塚公美会長が「今回は20回目の記念の会。わきあいあいとおしゃべりをしながら楽しんでほしい」とあいさつ。
開会後は、黄金保育園と大山保育園の園児たちが元気いっぱいに歌や踊り、和太鼓演奏を発表。園児たちのかわいらしい発表に会場からは大きな拍手が送られた。
「懐かしの歌謡ショー」では、鶴岡市出身の演歌歌手、吉住貴則さんが美空ひばりの「青い山脈」など、懐かしい歌の数々を美しい歌声で披露。参加者も「リンゴの唄」や「故郷」などを一緒に歌って楽しんだ。
その後、鶴岡市役所健康課保健師の丸山直美さんが「楽しく体を動かして健康長寿」と題して講演。いつまでも自分の足で歩き続けていくために筋力とバランス能力の維持・強化の重要性を学び、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)を予防するトレーニングを実践した。
昼食には、同会協力員による手作り弁当が振る舞われ、アトラクションや交流会も行われた。

美しい歌声が紡ぎだす懐かしの歌謡曲に盛り上がった

筋力やバランス能力を高めるトレーニングを実践

会員が協力して弁当を作った

おいしい手作り弁当で楽しく会食した
洋食のテーブルマナーを学ぶ・きらめきカレッジ
JA鶴岡は11月16日、東京第一ホテル鶴岡のレストラン「モナミ」で女性大学「きらめきカレッジ」の第4回講座を開き、23人が受講した。洋食のテーブルマナーを学び、食事を楽しんだ。
講師のレストラン「モナミ」店長の丸山由利加さんが、食事中のタブーや、フォークやナイフなどカトラリーの使い方など、西洋料理をスマートに食べるポイントを説明。説明を受けた後、学んだことに気を付けながら、食事を味わった。JA鶴岡のファーマーズマーケット「もんとあ~る」の野菜を使用した料理も並び、趣向を凝らした料理に舌鼓を打った。
参加者は「慣れてるつもりでも意外に知らないことも多く勉強になった。マナーに気を付けておいしく食べることができた」と話した。
「JAの時間」では、同JA金融部共済課の小松恵里子推進係長が、JAの共済事業や「生活傷害共済」を紹介した。参加者からは「保険のことは夫にまかせきりだったが、改めて話し合ってみたい」との感想が聞かれた。

テーブルマナーに気を付けながら、食事を楽しんだ
秋の感謝祭2018を開催
JA鶴岡セレモニー・プリエール鶴岡は11月17日、「秋の感謝祭2018」をプリエール鶴岡で開いた。
来場者も年々増え、過去最高の412人(207世帯)が来場。
会場では、葬儀・法要の事前相談をはじめ遺品供養やペット供養について紹介された他、さまざまな年代の方も楽しめるように抽選会、キッズコーナー、無料の飲食コーナーが設けられた。
また、特別企画として生花祭壇作りの実演とハーバリウム体験教室が行われ、多くの来場者でにぎわった。人形供養の受付も行われ、思い出の詰まった人形やぬいぐるみなどが持ち寄られた。
来場者からは「いざという時のため会場の見学と相談ができたので良かった」との感想が聞かれた。
この催事は、提携先セレモニーホールであるプリエール鶴岡を身近に感じてもらいながら、日頃の感謝をこめて開かれ、今年で5年目。

空くじなしのお楽しみ抽選会は大好評。

好みの花材を選びながらオリジナルのハーバリウムを作る来場者。
米粉・もち米粉を使った料理講習会・女性部上郷支部
JA鶴岡女性部上郷支部は11月15日、鶴岡市の三瀬コミセンで「米粉・もち米粉を使った料理講習会」を開き、部員20人が参加した。
米粉ともち米粉を使って、くじら餅、ネギ味噌おやき、米粉ギョウザスープの3品を作った。
参加した部員は「くじら餅の作り方が簡単で良かった。家にある野菜で作れて米粉の活用方法を知ることができた。製粉も利用してみたい」と笑顔で話した。
女性部では部員の特典として、うるち米の製粉を1㌔あたり200円のところ、半額の100円で利用することができる。製粉はファーマーズマーケット「もんとあ~る」3店舗で受け付けている。

米粉でおやきとギョウザと作る部員

完成した料理
女性部軽スポーツ大会で交流深める
JA鶴岡女性部は11月10日、部員の健康増進と交流を目的とした「軽スポーツ大会」を鶴岡市朝暘武道館で開き、140人が参加した。
はじめに、鶴岡市レクリエーション協会インストラクターの鎌田博子氏指導による軽体操を全員で行い、身体をあたため競技にのぞんだ。競技は6支部が赤・青・白・黄組の4組に分かれ、全5種目に挑戦。新種目の「お手玉投げ競争」は、点数の書かれた箱にお手玉(新聞紙を丸めた玉)を何個入れられるかを競う競技。出場者は、高得点の箱に狙いを定めてお手玉を投げ入れていた。女性部員が持ち寄った野菜を使う「野菜はかり競争」では、今年も多くの野菜が集まった。ダイコンやハクサイなどの野菜をかごに入れては持ち上げ、「まだ軽いからもう1個足そう」など話し合いながら時間いっぱいまで悩んでいた。
熱戦を繰り広げた結果、赤組が見事優勝。
また、個人賞には「応援がんばったで賞」に五十嵐秀子さん(北支部)と「玉送り上手だったで賞」に玉羽勇子さん(上郷支部)の2人が選ばれた。
今年度の成績は次の通り。
・優勝 赤組(南・大山)
・準優勝 青組(上郷・西郷)
・第3位 黄組(大泉)
・第4位 白組(北)

狙いを定めてボールをシュート。

チーム内で話し合いながら、野菜の重さを吟味していた。

赤組優勝おめでとうございます。
第28回JA山形県大会 改革すすめ危機突破へ
JAグループ山形は11月5日、山形市の山形テルサで第28回JA山形県大会を開き、県内各JAの役職員約750人が参加。JA鶴岡では役職員28人が参加した。
超高齢化と人口減少の進行、農業の担い手や労働力不足、政府による農協改革や農政改革、環太平洋連携協定(TPP)11・日欧経済連携協定(EPA)の発効、日米TAG交渉など、わが国の食料・農業・農村を取り巻く環境は厳しさを増している。
これらの危機突破に向け、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の創造的自己改革の実践と、JAの盤石な経営基盤の確立を通じて、組合員とともに農業と地域の未来を切りひらいていくとの決議を採択した。
各JAでは、各地域の実情に応じた具体策に取り組んでいく。

今後3年間の方針を決議したJA山形県大会
地元産の新米に舌鼓/第3回あぐりスクール
JA鶴岡は11月3日、第3回あぐりスクールを開き、市内外の小学3~6年生の親子12組35人が参加した。
はじめに、JA職員の菅原隼希指導員からJA鶴岡大泉カントリーエレベーターの貯蔵能力や機械の仕組み、米ができるまでなどの説明を受けた後、同施設内を見学。
参加した児童は「カントリーエレベーター内は専門工場という感じがし、たくさんの米が入ることがわかった」と笑顔を見せた。
引き続き、同市農村センターを会場に、管内で生産された新米「雪若丸」「つや姫」「はえぬき」「コシヒカリ」「ひとめぼれ」5品種の食べくらべを行った。品種あてクイズの他、「この本だいすきの会」庄内支部のメンバーによる読み聞かせも行われ、充実した時間を過ごした。
次回は、2月11日(月)に冬野菜の収穫体験を行う予定。


消費税軽減税率・収入保険制度を学ぶ
JA鶴岡は11月1日、鶴岡市の東京第一ホテル鶴岡でJA鶴岡農政対の研修会を開いた。関係者約80人が出席した。
佐藤茂一組合長はあいさつで、「2018年産米は予想外に大きく減収した。稲刈り前の作柄概況報道では平年並みであったことから農業共済の被害申告を出す人はほとんどいなかったと思う。JA鶴岡では18年産米の主要6品種60kgにつき600円の仮精算を11月に実施し、米の減収支援策として異常気象対策資金を創設した。また、園芸振興対策費の支出など、組合員の所得増大のために全力を尽くす」と述べた。
研修会では、「消費税軽減税率導入における課題と影響」と題して講演した税理士の栗山賢陽氏は、消費税の課税の仕組みと農作物の販売に軽減税率制度が導入されることを説明し、軽減税率をめぐる課題や23年から導入されるインボイス制度についても説明した。
また、「収入保険制度の内容について」と題して、農業共済組合連合会主事の髙橋秀氏と山形県農業共済組合庄内支所収入保険推進課長の佐藤秀樹氏から19年1月から始まる収入保険の仕組みや加入申請の具体的な方法が説明された。高橋氏は、収入保険は青色申告を行っている農業者が加入することができ、自然災害だけでなく、価格の下落なども含め、さまざまなリスクから農業経営を守る制度だと伝えた。

収入保険制度を説明する髙橋氏