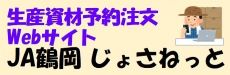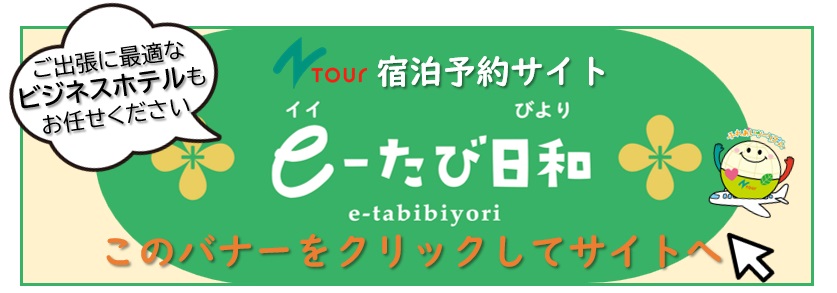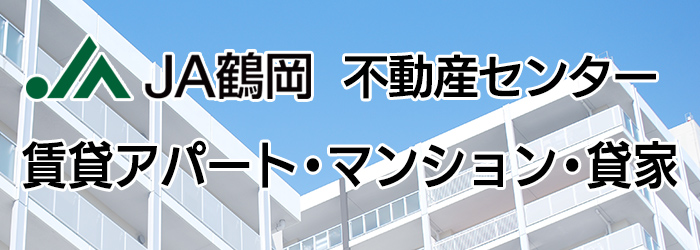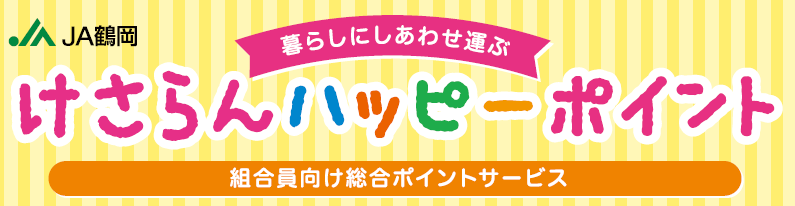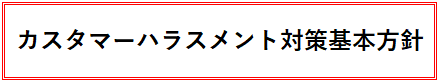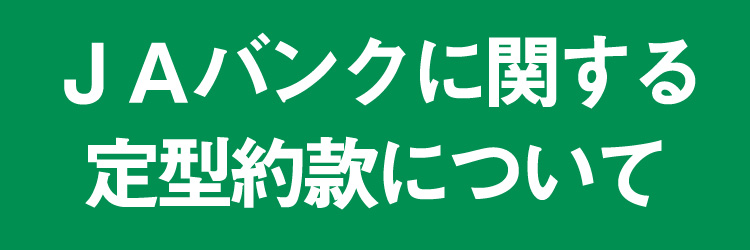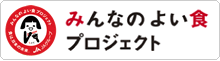第16回北支所グラウンドゴルフ大会を開く
JA鶴岡北支所は10月13日、鶴岡市の櫛引総合運動公園で第16回グラウンドゴルフ大会を開き、47人が参加。
支所管内の地域住民がグラウンドゴルフを通じ、交流とふれあいを図りながら、互いの技術の研さんと健康維持増進を目指すことを目的に毎年開いており、今年で16回目。
実行委員長の佐藤正さんが「今日は天候にも恵まれ、無事大会を楽しめることがなにより。最後まで緊張の糸を切らさずプレーしよう」とあいさつした。JA鶴岡の佐藤茂一組合長と佐藤実行委員長が始球式を行った。
秋晴れの空の下、4~5人ずつの11チームに分かれ、男女オープンの個人対抗で、8ホール3ゲームの24ホールで腕を競った。
熱戦の結果、ホールインワンを3回出した安丹の吉田健男さんが総打数50打の好成績で優勝した。2位は砂田町の菅原勝子さん、3位は砂田町の菅原利一さんだった。
吉田さんは「自己ベストを更新して優勝できた。来年もみんなでグラウンドゴルフを楽しもう」と話した。

プレーを楽しむ参加者

成績上位者(左から菅原勝子さん、吉田さん、菅原利一さん)

みんなで記念写真♪
もんとあ~る「庄内柿」の目揃い会を開く
JA鶴岡産直課は10月10日、鶴岡市のもんとあ~る白山店で「庄内柿」の目揃い会を開いた。
今もんとあ~るには、秋の味覚である梨やシャインマスカットなどのフルーツが盛り沢山となっており、特産である庄内柿が並ぶ時期となった。
今年度、庄内柿の出荷登録をしている産直会員は35人。今年は猛暑の影響で日焼け果が散見される。脱渋(だつじゅう)をすると日焼け部分が軟果するので選別に注意することや熟度など出荷規格の注意点を確認した。
JAの園芸指導係は「箱物は大切な方への贈答用で使用される。クレーム防止のため選別の徹底をお願いしたい。」と呼び掛けた。

店頭に並ぶ庄内柿。

出荷規格を確認する生産者。
長ねぎ目揃い会 出荷規格を確認
JA鶴岡長ねぎ専門部は10月6日、鶴岡市のJA鶴岡北部集出荷場で、長ネギの目揃い会を開いた。生産者、関係職員ら約30人が参加した。
渡部昌良司専門部長は「7月以降の高温により土寄せなどなかなか進まない状況であったが、稲刈り後気温がやっと下がってきたので、防除・消毒・土寄せをきちんと行い、良いネギを全国に届けよう」とあいさつした。
JAの園芸指導係が出荷規格を各等階級の白根の長さや曲がり、太さなどの基準を説明。根切りの程度や箱詰めの向きなど注意点を伝えた。
JAの販売係は「全国的に数量が少ないので単価は好調である。10月中旬頃からは他産地も出てくるので、早めの出荷と1本でも多くの出荷をお願いしたい」と呼び掛けた。
出荷は11月中旬にピークを迎え、12月中旬頃まで予定されている。

長ネギのサンプルを確認する生産者
サヤインゲン出荷規格を確認
JA鶴岡サヤインゲン専門部は10月4、5の両日、鶴岡市のJA西郷選果場と北部集出荷場で抑制栽培サヤインゲンの目揃い会を開いた。目揃い会初日は部会員約20人が参加し、出荷規格などを確認した。
JAの園芸指導係が各等階級の長さや太さ、品質、形状などをサンプルを提示して説明した。箱詰めは量目を確認し、注意点を伝えた。JAの販売係は「猛暑の影響で全国的に出荷量が少ない。10月に入り福島県産などが出てきたが出荷量は少ない。高値
での有利販売に努めていきたいので1箱でも多くの出荷をお願いしたい」と呼び掛けた。
抑制栽培のサヤインゲンは同専門部で78人で栽培し、出荷は11月下旬まで続く予定だ。

サンプルを確認する生産者(西郷選果場)
子どもたちに元気と笑顔を 産直会員が旬の農産物を提供
JA鶴岡ファーマーズマーケット「もんとあ~る」は9月27日、庄内地域の子どもたちに食事を無償提供する「庄内ちいき食堂」に、産直会員より提供いただいた食材を贈った。芋煮用にサトイモやシイタケ、長ネギ、デザート用にブドウ「シャインマスカット」が提供されたほか、カボチャやコマツナ、和梨や洋梨などの食材は参加した各家庭にプレゼントされた。
「庄内ちいき食堂」は、2021年12月に、代表の疋田司さんが食を通じて子どもたちに元気と笑顔を届けたいと運営をはじめた。近年は、毎月最終水曜日に酒田市と鶴岡市の会場を交互に開いており、食事を提供するほか、食材や日用品、ぬいぐるみなどの無償提供や、おもちゃなどを用意し子どもたちがたくさん食べて、元気に遊べるように企画されている。
この日は鶴岡市の第2学区コミュニティ防災センターを会場に、庄内地域に住んでいる18組51人の親子に芋煮や新米のおにぎりなど、旬の食材を使った食事をふるまった。
JA営農販売部産直課の高橋千津課長は「産直会員の皆さまにはたくさんの野菜や果物を提供していただき感謝している。今後も子どもたちに喜んでいただけるようもんとあ~るでも協力していきたい」と話した。
「もんとあ~る」が食材を提供するのは、5月に続いて2回目。

産直会員の皆さまからいただいた食材の数々

デザートのシャインマスカットを手ににっこり笑顔♪

家庭用に食材も提供されました!
第3回きらめきカレッジ パーソナルカラーでメイクレッスン
JA鶴岡は9月21日、鶴岡市農村センターで第3回「きらめきカレッジ」を開き、受講生13人が参加した。
今回は「パーソナルカラー診断&メイク」と題し、講師に美容室OASISの大宮希店長とスタッフの髙橋あいこさん、榎本華鈴さんを迎え、メイクを学んだ。
最初に「パーソナルカラー診断自己診断チェックシート」を使い、自分の肌の色や瞳の色などの質問項目から自分に似合うカラーを診断。その後、自分のカラーに合うアイシャドウやリップなど美しく仕上げるメイクアップのコツを丁寧に教わった。
大宮店長は「自分に合うカラーを取り入れることで、さらにステキに魅せることができる。パーソナルカラーを生かして、メイクを楽しんでほしい」と話した。
参加者は「診断は難しかったが、自分のタイプを知れてよかった。ファッションやメイクに取り入れてみたいと思う」と話した。
「JAの時間」では職員が、「国消国産と農業」をテーマに課題を共有し、それぞれの地域の地産地消の積み重ねが農業を応援することにつながることや当JAの産直「もんとあ~る」の紹介をした。

メイクアップのコツを話す大宮店長㊧と榎本さん㊨

「JAの時間」では国消国産を紹介
年金友の会グラウンドゴルフ大会を開催!
JA鶴岡では9月14日、鶴岡市櫛引総合運動公園で第16回となる年金友の会グラウンドゴルフ大会を開き今年は112人の会員が参加した。最初に大会会長の佐藤茂一組合長はあいさつで「今年は暑く、なかなか練習ができなかったと思います。誰でも優勝が狙える日、熱中症に気を付けてプレーを楽しんでください」と述べた。続いて実行委員長である年金友の会連絡協議会の石井善兵衛会長が「日頃の練習の成果を発揮し、楽しい時間を過ごしてください」と述べた。その後、選手宣誓をした大泉地区の後藤隆さんは「今日は認知症予備軍であることを忘れ頑張りたい」とユーモアを交えた宣誓で会場の笑いをさそった。今年は稲刈りが早まり例年より参加者が少ない3人~5人の男女オープンの組で個人対抗戦を3ラウンド24ホールで競った。結果、南地区の丸山直さんがホールインワン等の好プレーを発揮し見事優勝。准優勝は北地区の菅原利一さん、3位は南地区の五十嵐としさんとなった。

開会宣言。
.jpg)
選手宣誓する㊨大泉地区の後藤隆さん。
.jpg)
始球式(㊧佐藤組合長、㊨石井善兵衛さん)
.jpg)
プレーを楽しむ参加者。
.jpg)
優勝した㊧南地区の丸山直さん。
斎小学校の児童が稲刈り体験 青年部南支部
鶴岡市立斎小学校の5年生14人は9月8日、学校近くの三浦直樹さんの田んぼで稲刈りを体験した。
JA鶴岡青年部南支部の指導のもと、5月に植えた「はえぬき」を鎌で収穫。同校では、食農教育の一環として毎年、田植えから稲刈りまでの稲作を学んでいる。
上野拓支部長が鎌の持ち方や稲を刈る時のコツを指導。児童は鎌を使って1株ずつ丁寧に刈り取った後、稲杭(いなぐい)に稲束を掛けて自然乾燥させる杭掛け作業を体験した。
児童は「田んぼに埋まって大変だったけど、楽しかった。食べるのが楽しみ」と話した。

いっぱい刈ったよ!

杭掛けを説明する青年部員

稲刈り体験楽しかったよ♪
ネットメロン精算報告会を開く
JA鶴岡と西郷砂丘畑振興会は9月8日、鶴岡市の湯野浜温泉「亀や」で、2023年度ネットメロン精算報告会を開いた。生産者、JA役職員、市場関係者など約125人が参加した。
出荷数量は約49万9000㌜と前年よりも約5000㌜増えた。端境期などの影響もあったが、販売高は11億1900万円と目標には届かなかったものの3年連続11億円を突破した。
西郷砂丘畑振興会の佐藤重勝会長は「猛暑の影響で、出荷数量が目標の50万㌜には届かなかった。面積は年々減少傾向にあるが、平準出荷が非常に重要になるので、鶴岡の高品質で安心・安全なメロンを消費者にお届けするためにも皆さんからさらなるご協力をいただきたい」とあいさつした。
作柄状況や販売経過を報告。ハウス作型は概ね順調に推移したが、7月下旬からの高日照により露地作型はしおれや日焼けなどの症状が発生し、下位等級の発生が多くなった。今年度は端境期間が長くなってしまったため次年度以降、端境対策を強化していくことを確認した。
市場関係者からは、試食宣伝販売が今年から解禁され販売のツールが追い風となっている。出荷時期やピーク時期情報の事前共有で安定販売へつなげたいが、数量が足りていないので面積の維持・拡大をお願いしたいと要望された。
また、高品質なメロンを栽培した生産者と集落を対象に共励会表彰が行われ、個人の部は下川上の本間隼平さん。集落の部は下川中が受賞した。

挨拶する佐藤振興会会長

共励会表彰受賞者(㊧下川中集落の代表阿部桂汰さん、㊨下川上の本間隼平さん)
枝豆用色彩選別機の実演会を開く
JA鶴岡は9月5日、鶴岡市のJA鶴岡中央センター農機工場で枝豆用色彩選別機の実演会を開いた。生産者とJA職員ら約30が参加した。
農業機械メーカーの職員が、機械の使用方法や性能を説明後、実際に機械を動かして選別の流れを実演した。
色彩選別機は、高性能カメラで枝豆の表面(変色・虫食い・濁点など)を識別して不適合品を吹き飛ばし、人員やコストの削減が見込める。
主力品種のエダマメ「だだちゃ豆」の出荷にかかる人手と手間を省力化する点で注目を集めており、JAでは今後も実演会の企画を予定している。

枝豆用色彩選別機の説明を受ける生産者