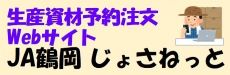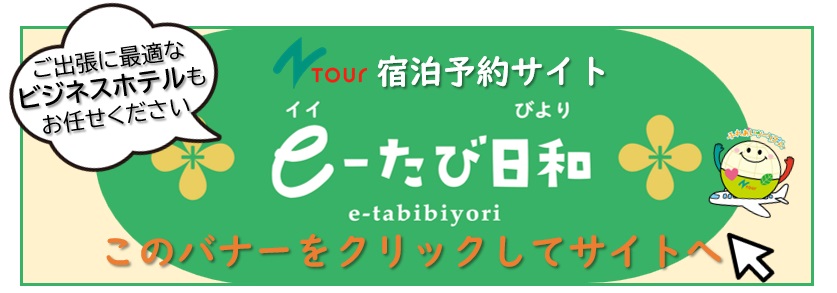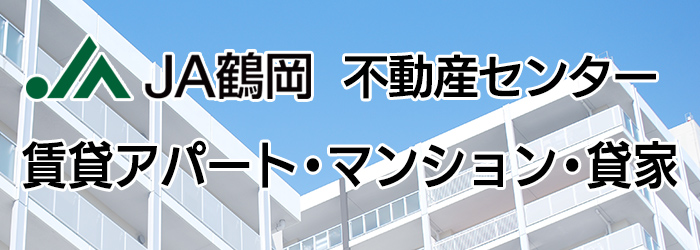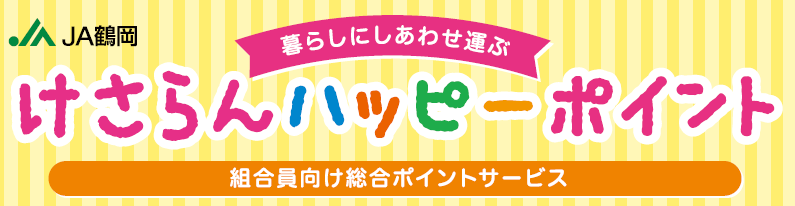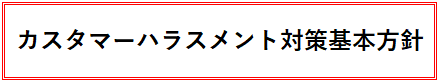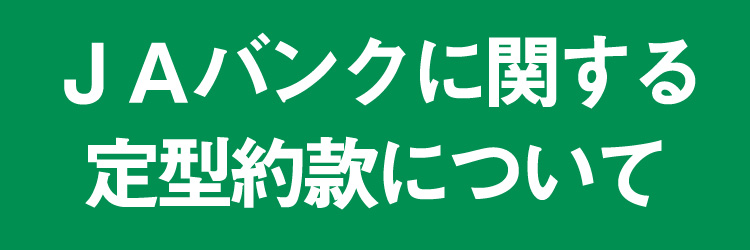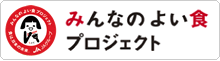鶴岡の花を使ったフラワーアレンジメント講習/第5回きらめきカレッジ
JA鶴岡は2月21日、鶴岡市農村センターで女性大学「きらめきカレッジ」第5回を開き、受講生21人が参加した。管内で花を生産している佐藤民子さんが講師を務め、地元産の花を使ったフラワーアレンジメントに挑戦した。
参加者は、鶴岡産のアルストロメリア、ストック、キンギョソウ、桜など7種類の花を使い、思い思いの作品を仕上げた。
「JAの時間」では、「鶴岡の花」をテーマに、同JA花き振興部会の取り組みや、花の栽培から出荷までの流れ、若手花農家の花栽培への思いなどを紹介した。
参加者は「地元でこんなにたくさんの花を生産していることを知って感動した。鶴岡の花で素敵なアレンジが完成してうれしかった」と話した。
講座終了後には3期生の卒業式を行った。2年のカリキュラムを終了した受講生に佐藤茂一組合長が修了証書を手渡した。
きらめきカレッジは5月に開校し、味噌作りや、体のゆがみ矯正体操、洋食のテーブルマナーなどを学び、自分を磨きながら親睦を深めてきた。
卒業生は「地元産の大豆を使った味噌や梅酒作りなど、JAならではの企画で楽しい2年間を過ごすことができた」と話した。

佐藤さん(中央)の指導で作品を仕上げる受講生

素敵なアレンジが完成しました

卒業おめでとうございます
ワナゲ交流会を開く/JA鶴岡年金友の会
JA鶴岡は2月22日、鶴岡市農村センターでJA鶴岡年金友の会ワナゲ交流会を開いた。会員149人が参加し、上位を目指して熱戦を繰り広げた。競技終了後には懇親会を開き、会員同士の親睦を深めた。
同交流会は「心と健康を輪でつなぐ」を合言葉に会員相互の親睦と、健康増進に寄与することを目的に毎年開いている。
28チームに分かれて一斉にプレイを開始し、一人3ゲームを行った。白熱したプレーの結果、個人戦では同市文下の五十嵐俊治さんが、パーフェクトも含めて合計630点の成績で優勝。チームの合計得点で競う団体戦では「黄金A」チームが優勝した。

試合に臨む会員たち
ハウストマト専門部栽培講習会を開く
JA鶴岡ハウストマト専門部は2月21日、南支所で栽培講習会を開いた。関係者15人が参加。
2019年から収量や品質面の向上が見込めるトマト「りんか409」の作付けを計画している事から、株式会社サカタのタネ営業第一部東北支店の東太郎氏より品種特性や草勢を維持するための栽培ポイントを学んだ。
活着時の注意点や温度、湿度、潅水(かんすい)、摘果管理や茎が折れた場合の対応などが説明され、出荷時の色づきもこれまでの品種と変わるため、目ぞろえを行うよう呼び掛けた。
参加者からは、発芽時の温度管理やしおれ対策など、これまでの栽培管理との違いについて質問が出された。

新たに作付けするトマトについて学ぶ参加者
もんとあ~る全体会議で今年度総括と次年度計画を確認
JA鶴岡ファーマーズマーケット「もんとあ~る」は2月20日、鶴岡市のJA大泉支所で全体会議を開いた。産直出荷会員107人が出席した。2018年度の総括と19年度の計画を確認した。
18年度は、7月に、より一層親しまれる直売所をめざし店舗名を「もんとあ~る」に改めリニューアルオープンしたことで、市内での認知度が高まり、年間の来場者数は昨年度より1万人増の約49万人を突破した。一方、夏の高温と大雨、秋の台風により、収穫量と出荷量が減り、産直品が不足した。
19年度は、「新鮮さ」と「品質の良さ」のレベルアップを図るため、検品体制の強化と栽培講習会、目ぞろえ会、品質クレームへの対応強化に取り組む。不便さを軽減するために、商品を1カ所で買い求められるよう「ワンストップショッピング」へ対応する。産地間提携品などの取り扱いや、イベント開催による魅力的な店舗づくりに努めていくことなどを確認した。
ほかに、加工表示の注意点や、農薬の適正使用、栽培履歴書の提出についても呼び掛けられた。
佐藤茂一組合長による「JA鶴岡の情勢報告及び機構改革、産直の役割について」と題した講話では、「人生100年時代。元気に長生きしながら、楽しみの農業、生きがいの農業に取り組んでいただき、もんとあ~るに積極的に出荷してほしい」と激励した。
五十嵐正谷もんとあ~る運営委員長は「所得の向上を目指して、会員同士団結してがんばろう」と呼び掛けた。

JAの情勢報告と産直の役割について講話する佐藤組合長

18年度の総括と19年度計画を確認する参加者
大山支所 担い手・若手農業者研修会を初開催
JA鶴岡大山支所は2月16日、鶴岡市のJA大山支所で担い手・若手農業者研修会を開いた。関係者18人が参加。
支所管内の20から40代までの農業者や後継者候補など今後の営農を担う方々を対象に初めて企画、就職している方も多く集落を超えて交流することも少ない事から、農業への関心を高め、仲間作りと交流の場として研修会を開いた。
支所青年部の3人が各自の栽培品目や面積、就農状況を説明し、職員より農協事業を紹介した。その後、懇親会も行われ参加者は親睦を深めた。
JAの佐藤治久理事は「こうやって交流する事が大事。家や地域、悩みなどいろいろと情報交換してもらいたい」と話す。

若手農家の就農状況を聞く参加者
家庭料理を持ち寄り豊かな食文化を再確認/女性部上郷支部
JA鶴岡女性部上郷支部は2月16日、第9回「いただきます!」を鶴岡市の上郷コミュニティーセンターで開いた。女性部員や豊浦・上郷地域の女性住民、役職員含め32人が参加した。
参加者が持ち寄った昔ながらの家庭料理や伝統食を味わうことで、先人の知恵を学びながら地元の食文化や食材の良さを再発見し、地域の交流の場とすることが目的だ。
赤飯やくるみ豆腐、わらびあえ、甘酒など、33品の多彩な料理をビュッフェ形式で試食した。参加者は「自分では作らない料理をたくさん試食できて楽しい企画だ。毎年楽しみにしている」と話し、作り方を教え合いながら味わっていた。
上郷保育園栄養士の板垣舞さんから、上郷保育園が取り組む食育の講話も聞いた。青年部員と一緒に野菜の定植や収穫体験をし、収穫した野菜を使って調理実習をしていることを紹介。板垣さんは「収穫体験や、食べ物の働きや栄養、旬を教えることで、子どもたちの食への関心を高め、家庭や地域と連携して食育に取り組んでいきたい」と話した。

自慢の一品が並んだ会場

上郷保育園が取り組む食育について学んだ
けさらん愛、愛サービス 高齢者世帯に手作り弁当を届ける
JA鶴岡助けあいの会「けさらん愛、愛サービス」は15日、管内の高齢者世帯172世帯を訪問し、手作りの弁当を届けた。
鶴岡市農村センターで、会員31人が約300食の弁当を作った。地元産食材を使い「がんもと野菜の煮物のくずあんかけ」や「イタドリの煮物」、「アスパラ菜のからししょうゆあえ」「シソ巻き」「赤カブの漬物」など彩り豊かな弁当を完成させた。
石塚公美会長は「会員のまごころがたくさん詰まった弁当を食べてこれからも元気に暮らしてほしい」と話した。
弁当を受け取った三瀬の斎藤紀子さんは「毎年楽しみにしている。いつもありがとう」と笑顔で話した。
この取り組みは、組合員とその家族や地域住民で、おおむね70歳以上の高齢者のみの世帯を対象に、栄養バランスの良い食事を届けて健康づくりへの貢献を図る目的で毎年行われている。

弁当作りに励む会員。

172世帯にまごころを込めて作った弁当を届けた。

地元の食材がふんだんに使用された、彩り豊かな弁当が完成。
もんとあ~る 栽培講習会 花の栽培管理を学ぶ
産直課は2月13日、鶴岡市のJA鶴岡大泉支所で栽培講習会を開いた。関係者約42人が参加した。
直売所「もんとあ~る」で7月から秋彼岸まで出荷されるアスター、ケイトウなど5品目の花きの栽培管理について学んだ。
庄内総合支庁産業経済部農業技術普及課の黒坂美穂主任専門普及指導員が茎の曲がりを防ぐフラワーネットの使い方や各品目の播種(はしゅ)から収穫までの流れや栽培上の注意点やポイントについて説明した。
「もんとあ~る」では、花きの需要が高いことから品ぞろえの強化と生産者を増やすため新規生産者向けの講習会を初めて開いた。

もんとあ~るへの出荷に向けて花き栽培ポイントを説明した
パソコン技術を学ぶ 女性部西郷支部
JA鶴岡女性部西郷支部は2月4日、西郷支所を会場にパソコン講座を開いた。
この事業は、女性部員からパソコンの使い方を学びたいとの意見を受け、今年で2年目。職員が講師を務め、部員11人が参加した。
昨年の復習としてマウスを使ってクリックやドラッグといったマウスの動かし方を練習した後、ワードで図形や画像の貼り付け方法を学んだ。
文書作成の練習として女性部員募集のチラシ作成した。
参加者からは「文書に簡単に写真や図を入れることができたことに感動した。来年の年賀状作成に活用したい」との声が聞かれた。

パソコンの機器について学ぶ参加者。

ワードの使い方を教える講師。
平成30年度ミニトマト専門部実績検討会を開く
ミニトマト専門部は2月8日、鶴岡市のJA西郷支所で実績検討会を開いた。関係者約130人が出席した。
2018年度は、気温の影響により収穫始めから小玉傾向での出荷となったが、マルハナバチの導入が増えた効果により、つや無し果の発生が減少し、栽培面積も増えた事で出荷数量は増え、販売単価は前年比10%増と伸長し過去最高の販売額を記録した。
木村和司専門部長は「18年度は、過去最高の販売額を残せた。今後もミニトマトと言えば鶴岡産と消費者に周知してもらえるよう安心で高品質なミニトマトを届けていこう」と呼び掛けた。
市場関係者からは、市場環境や販売動向が報告され、他産地の作付面積が増えている事、より品質を高めるため、市場独自に検品している事が伝えられ、より一層の品質の向上、選別の徹底を要望された。
19年度は、高温・アザミウマ対策の徹底、マルハナバチ導入の推進による品質の向上、9・10月を中心に企画販売の充実や販路拡大に取り組んでいく。

2018年度を総括する木村専門部長