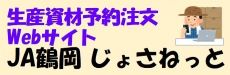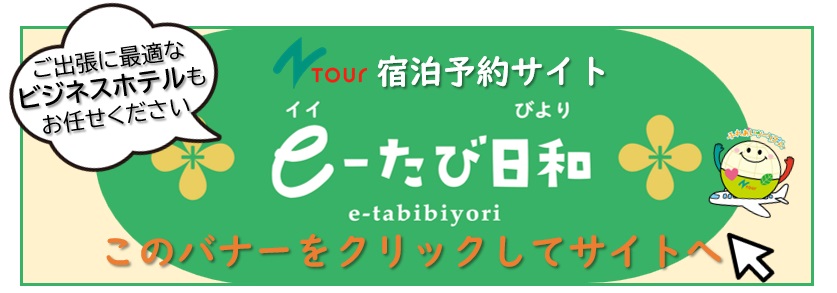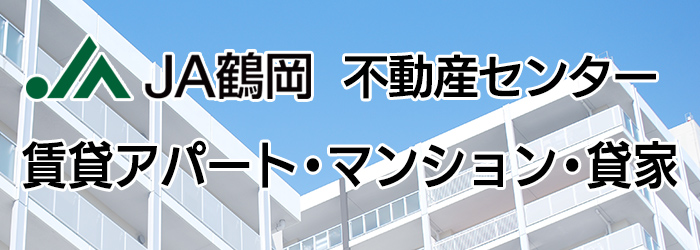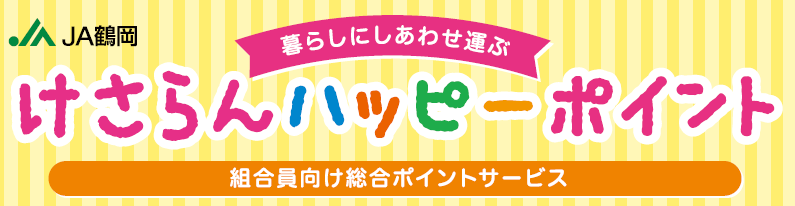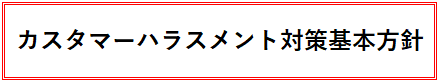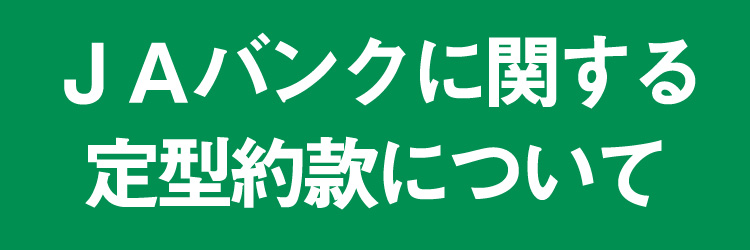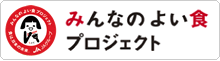ワナゲ交流会を開く/JA鶴岡年金友の会
JA鶴岡は2月20日、鶴岡市農村センターでJA鶴岡年金友の会ワナゲ交流会を開き、約140人の会員が参加した。
同交流会は、「心と健康を輪でつなぐ」を合言葉に会員相互の親睦と、健康増進に寄与することを目的に開かれており、今年で2回目。
開会式では、伊藤淳専務が「健康に留意しながら、日ごろの練習の成果を十分発揮してほしい。交流会を契機に、融和と健康増進に努めてほしい」とあいさつした。
その後26チームに分かれて一斉にプレイを開始、一人3ゲームを行った。
寒さを吹き飛ばす熱戦が繰り広げられた結果、個人戦では同市高坂の長谷川富子さんが、パーフェクトも含めて合計630点の成績で優勝。
また、チームの合計得点で競う団体戦では「田川A」チームが2年連続優勝となった。

高得点を狙う参加者

優勝した長谷川富子さん(中央)
JA鶴岡女性大学「第5回きらめきカレッジ」手作り茶わんでお茶を楽しむ
JA鶴岡は2月20日、鶴岡市農村センターで女性大学「きらめきカレッジ」第5回を開き、受講生11人が参加した。「和の心 お茶を楽しむひととき」をテーマに、茶のたて方や茶席の作法を学んだ。
裏千家の同JA五十嵐千代美理事から、長芋ときな粉を使った簡単団子の作り方や、茶のたて方などを学び、五十嵐理事がたてた薄茶をいただいた。
その後、第1回講座で作成した抹茶茶わんを使って、各自が茶をたて、緊張した表情ながら、茶や菓子をゆっくりと味わっていた。
参加者は「抹茶のたて方や作法などを学べて勉強になった。自分で作った茶わんでお茶が飲めてうれしかった」と話した。
「JAの時間」では、市民を対象に食と農への理解を深める「あぐりセミナー」や、親子で農業体験をする「あぐりスクール」などの生活文化事業について紹介した。
講座終了後には2期生の卒業式を行った。2年のカリキュラムを修了した卒業生たちは、学長の佐藤茂一組合長から修了書を受け取り、「いろいろな体験ができ、楽しくためになる時間だった」と振り返った。
佐藤茂一組合長はあいさつで「卒業おめでとう。趣味を持ってこれからの人生を楽しんでほしい。今後もぜひJA鶴岡の事業に参加してほしい」と述べた。
「きらめきカレッジ」は、管内の若い女性を対象に、2年1期の全10回でさまざまな分野の講座を仲間と楽しく学び、自分を磨くことを目的に、2015年に開校。2018年春には、4期生を募集する。

茶のたて方を学ぶ受講生。

簡単和菓子ができました。

2期生と3期生で記念写真。
けさらん愛、愛サービス 高齢者世帯に手作り弁当を届ける
JA鶴岡助けあいの会「けさらん愛、愛サービス」は16日、管内の高齢者世帯152世帯を訪問し、手作りの弁当を届けた。
鶴岡市農村センターで、会員30人が285食の弁当を作った。地元産食材を使い、「ちらしずし」や「サトイモ巾着の煮物」、「いたどり煮」「菊とホウレンソウのゴマあえ」「ワラビのしょうゆ漬け」など彩り豊かな弁当を完成させた。
髙橋信子会長は「山菜を使った2品や、もうすぐおひなさまなのでちらしずしを取り入れた。この弁当を食べてこれからも元気に暮らしてほしい」と話した。
弁当を受け取った西京田の佐藤おゆきさん(89)は「毎年おいしくいただいている。どうもありがとう」と笑顔で話した。
この取り組みは、組合員とその家族や地域住民で、おおむね70歳以上の高齢者のみの世帯を対象に、栄養バランスの良い食事を届けて健康づくりへの貢献を図る目的で毎年行われている。
 」
」
弁当作りに励む会員。

152世帯に手作りの弁当を届けた。

春を感じる弁当が完成した。
中華料理作りに挑戦/女性部大泉支部虹の部会
JA鶴岡女性部大泉支部虹の部会は14日、冬の地場野菜を使った中華料理をテーマとした講習会を鶴岡市農村センターで開いた。13人が参加。
JA鶴岡の佐藤綾音生活文化事業担当を講師に、旬のハクサイ、ニンジン、長ネギなどをふんだんに使ったあんかけ焼きそばや肉まん、麻婆豆腐など5品を調理した。
佐藤さんは味付けのポイントや肉まんの包み方などのコツを説明し、参加者は声を掛け合い協力して手際よく取り掛かった。
参加した石川志津さんは「寒気が強くハウスの冬野菜もなかなか育たないが、地元食材を使った中華風料理を覚えられてよかった。にぎやかで楽しい料理講習会だった」と述べた。

肉まんの包み方を学ぶ参加者。

地場野菜を使った中華料理が完成。
『すまいる通信Vol.11』を発行しました
当JAすまいるプラザでは、暮らしに笑顔をお届けする情報誌『すまいる通信Vol.10』を発行しました。
「すまいる通信」では、暮らしと住まいをサポートする「JA鶴岡すまいるプラザ」の事業内容や、取り扱いしている商品、お役立ち情報などを紹介しています。
●すまいる通信最新号(2018年2月発行)はこちらから。
長期共済達成大会でだるまに目入れ
JA鶴岡共済課は2月7日、鶴岡市の金融本店で2017年度長期共済達成大会を開いた。共済ライフアドバイザー(LA)や全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)関係者27人が出席。実績経過を報告し、だるまの目入れ式を行った。
1月31日付でJA共済推進目標ポイント180万ポイントを達成。今年度から保障の適正化を図る観点から目標ポイントを見直した。さらに、資産流出を防止するため、信用商品も含めたアドバイスを行うライフマネーアドバイザー(LMA)を新たに設置。将来にわたり「安心」を組合員に提供するため、推進はもちろん徹底した相談活動の実践を目指す。2年に一回全戸を訪問することを目標とした3Q訪問活動も継続していく。
佐藤茂一組合長は「職員の頑張りのおかげと感謝する。お客さまのニーズに沿って、共済推進はより安く、安心を提供する、この言葉を胸にこれからの職務に励んでほしい」と激励した。

だるまに目を入れる佐藤組合長
鶴岡産秋野菜の発展に向けて
西郷砂丘畑振興会は2月2日、秋野菜の生産・販売についての総括を行う2017年度秋青果物精算報告会を西郷支所で開き、西郷地域の生産者と市場関係者など約130人が出席した。
本間吉典会長は「今年も天候に悩まされた年となったが、主要品目のミニトマトの販売高が昨年を上回ることができたのは出荷いただいた生産者のおかげ。次年度以降も高品質出荷を目指してほしい」と述べた。
当日は、秋野菜で栽培者数が多いミニトマトやサヤインゲンはじめ、長ネギ、軟白ネギ、赤カブ、抑制メロンといった秋野菜主要品目の生育概況と販売経過が報告された。生産面では順調な出荷となり、販売面でも全体的に堅調な販売環境で推移し、特にミニトマトは過去最高の販売額となった。
消費地から産地への提言として、東一川崎中央青果株式会社野菜第2部部長の今井彰久氏は「鶴岡産野菜を求める声が多くあるので、今後も作付面積を減らさず、高品質出荷を目指してほしい」など集まった生産者らを激励していた。
同日開かれたミニトマト専門部実績検討会では、生産販売経過と出荷実績の総括が行われた。
本年度よりマルハナバチを本格導入したことで、出荷に大きなピークや谷間がなく、継続的に出荷することができ、またトマトトーン散布作業の省力化やつや無し果の発生抑制により正品率が高くなり、選別作業の省力化につながったことが報告された。

来年産に向けた意見交換が行われた。

消費地の声を報告する東一川崎中央青果(株)の今井部長(左)
甘酒料理に舌鼓/女性部南支部輝き部会
JA鶴岡女性部南支部は2月4日、鶴岡市黄金コミュニティ防災センターで料理講習会を開いた。
部員12人が参加し、健康食品として注目されている「甘酒」を料理の味付けや隠し味として使用した料理4品を作った。
甘酒で煮込んだ具だくさんのシチューは、ダイコンやニンジンなど旬の野菜の味をいかしつつ甘酒のやさしい甘みが引き立つ味わいになった。
フライパンピザは生地を丸く伸ばしていく作業を楽しみながらしていた。定番のベーコンやコーンをはじめ軟白ねぎやミニトマトなど地元の野菜をトッピングし、彩りも鮮やかなピザが完成した。
参加者からは「甘酒を味付けに使う発想がなかったので、これから料理に活用していきたい」との声が聞かれた。

楽しみながら調理をしていました

完成した料理の数々
高校生が郷土料理や行事食を学ぶ/女性部
JA鶴岡女性部は31日、山形県立鶴岡中央高等学校で伝統料理講習会を開いた。
食文化が多様化する中で地域の郷土料理や伝統食などの食文化を次の世代へ継承するために今年初めて企画。
鶴岡中央高校総合学科家政科学系列食物系2年の生徒20人が、女性部員6人の指導のもと、鶴岡の伝統料理である赤飯、納豆汁、ごま豆腐のあんかけの3品を作った。
はじめに女性部員の石塚公美さんが蒸し器を使った、本格的な赤飯の作り方を説明。赤飯ササギの煮汁の取り方や蒸し方のポイントなどを伝えた。蒸しあがったばかりのツヤツヤの赤飯を見た生徒からは「おいしそう」と歓声があがった。
また、ごま豆腐作りではすり鉢でごまをするところから調理を開始。各班に女性部員がつき、弱火でじっくり練っている生徒に「とろみがついてくると一気に固まるから注意して」などと声をかけながら調理を進めた。
昔ながらの作り方を学んだ生徒からは「すり鉢でごまをすったり、納豆をつぶしたりするのが大変だけど楽しかった」との感想が聞かれた。

頑張ってごまをする生徒。

地域に伝わる伝統の味が完成。

おいしくできました!
アルストロメリア・ストック実績検討会を開く
JA鶴岡アルストロメリア専門部とストック専門部は31日、鶴岡市の農業振興センターと北部集荷場でそれぞれ実績検討会を開いた。関係者延べ50人が出席した。
各実績検討会では、販売実績や各市場担当者から市場動向の報告、栽培管理について説明が行われ、今後の作付け品種の紹介・検討や来年度に向けての課題整理を行った。
アルストロメリアは、2017年の出荷数量が生産者の栽培管理により生育も順調で18万7千本と昨年を超える出荷となり、販売額も昨年を上回った。
市場からは、17年は厳しい状況だったが、色のバランスもよく安定して出荷していただいた。他産地が減少しているいることから今後も継続しての出荷を期待された。
また、ストックについては、例年よりも早めに出荷が始まり、本数、販売金額ともに昨年度同時期に比べて上回っている。しかし昨年度の最終実績には届いていないため、出荷後半で連日の寒さの影響もあり今後厳しい状況が続くが昨年度の出荷本数を超えようと呼び掛けた。
市場からは、天候に左右される状況だが、多くの出荷をお願いしたいと伝えられた。

アルストロメリア品種検討で今後の導入に向けサンプルを紹介した。

ストック専門部実績検討会では、来年度に向けて課題が検討された。