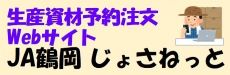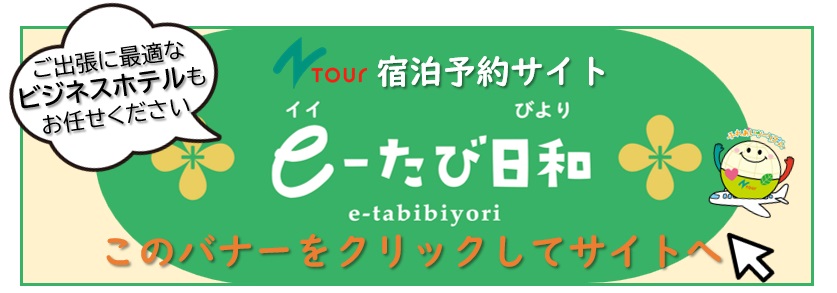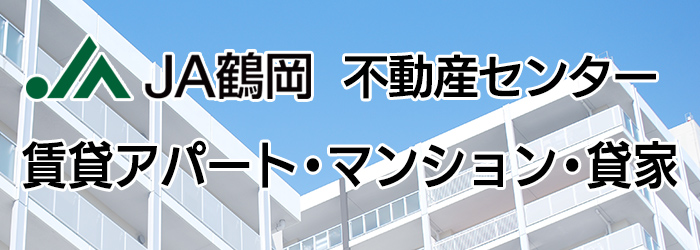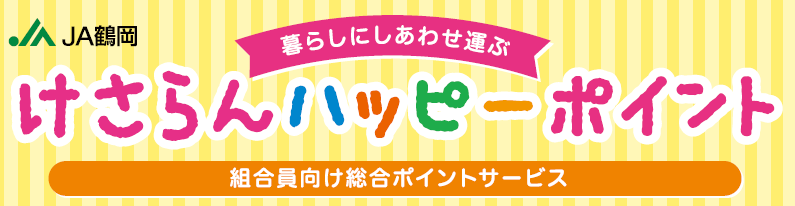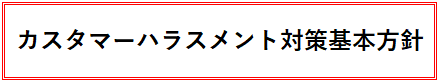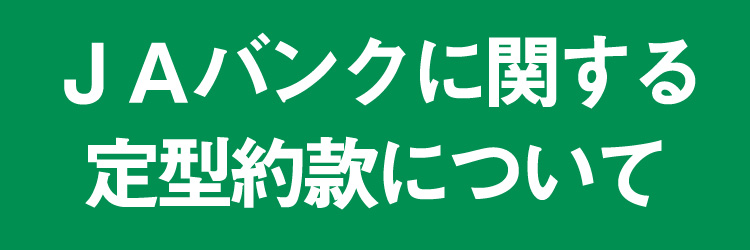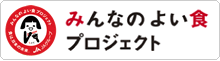あぐりセミナーで昔ながらの豆腐づくり
JA鶴岡は3月16日、鶴岡市農村センターで第5回JAあぐりセミナーを開いた。市民36人が参加した。鶴岡市のいとうファーム代表取締役社長の伊藤稔さんを講師に、講話と昔ながらの豆腐づくりを体験した。
前日に水に浸しておいた大豆をミキサーにかけて布でこしながら豆乳に加工。鍋に入れてかき混ぜながら煮た後、にがりを加え型に注いで固めた。参加者は「いい香りがする」「おいしい」など出来たての味を楽しんだ。
講話では、大豆と日本の食文化の関わりや、伊藤さんが全国の小学校で、大豆から学ぶ命の大切さについて教える取り組みについて紹介した。
JAの事業を紹介するJAの時間では、旅行事業や食材宅配、セレモニーなど、幅広い事業を取り扱う生活課を紹介した。
参加者は「手作り豆腐は手間かかるけど、食べてとてもおいしかった」と話した。

伊藤さんから豆腐作りのコツを聞く参加者。

大豆栽培について紹介する伊藤さん(中央)
産直館 新名称「もんとあ~る」に決まる
JA鶴岡が運営する直売所「産直館」の新名称が「もんとあ~る」に決まった。
新名称は全国から一般公募された2249点の中から鶴岡市在住の本間孝夫さんが考案した名称が採用された。16日に鶴岡市のJA鶴岡大泉支所で表彰式が行われた。
産直館という店名は、産直施設の総称として捉えられる事もあり、今年が15周年を迎えることから名称変更を企画した。
新名称は管内の方言である庄内弁で「山ほどある」を意味する「もんとある」に由来。地元の野菜や果物が山のように豊富にある直売所をイメージすることから採用された。
表彰された本間さんは「喜びと責任を感じている。名前にふさわしい施設になってもらいたい」と話した。
なお、最終選考に残ったほか4点の作者、原田あさみさん(神奈川県小田原市)、藤野智子さん(山形県鶴岡市)、吉村健二さん(埼玉県狭山市)、小寺光雄さん(愛知県名古屋市)にも米「つや姫」などの記念品が贈られた。
名称に続きロゴについても公募が始まっており、夏ごろには新名称でのリニューアルオープンを予定している。

表彰された本間孝夫さん(右)と佐藤茂一組合長
タグ :直売所 直売所 もんとあ~る
2018年産米種子の温湯消毒が最盛期 大泉育苗組合
鶴岡市大泉地区の大泉育苗組合では2018年産米水稲種子の温湯消毒作業が最盛期を迎えている。
3月初旬から作業が始まり18年度は過去最高数量の約13㌧が申し込まれ、一日に1㌧超える消毒作業が中旬頃まで行われる。
品種別に色分けされた袋に入れた種子を60度の温水に10分間浸し消毒、その後冷却、脱水、風乾後各生産者へ順次届けられる。
同育苗組合は、農薬成分を減らした安全安心な米の生産、販売に取り組むため、農薬を使わない温湯消毒を12年より始め、主に大泉地区の組合員が利用している。
また、地区内の大泉カントリーエレベーター(CE)が取り扱う米「つや姫」は、全量温湯消毒を行い安全安心の米生産に向けて取り組んでいる。

種子袋を温水より引き上げる作業員
若手農業者研修会を開く
JA鶴岡は13日、鶴岡市のJA鶴岡本所で若手農業者研修会を開いた。関係者15人が参加した。
市内で飲食店を営む庄内ざっこ店長齋藤亮一氏より、「食と農について考える飲食業からみたこれからの農業の可能性」と題した講演が行われた。
講演では、料理人から見た食材の魅力や美食の街スペインのビルバオ市での世界料理人交流事業での体験した事、食の現場から見た農業の魅力や今後の可能性について伝えた。
齋藤氏は「食育が大切、小さい頃からいろいろなおいしいものと触れ合う機会を作ることが食べる習慣につながっていく。
また、生産者の皆さんが情報を発信することで、いろいろな人とつながって売り上げを伸ばすことになる。顔が見える事で料理人も使ってくれる」と話した。
齋藤氏は、その後の懇親会にも参加。若手生産者と互いに思いを語り合った。

情報発信の重要性を伝える齋藤氏
花き振興部会 総会を開く
JA鶴岡花き振興部会は2月28日、鶴岡市の東京第一ホテル鶴岡で第29回総会を開いた。関係者約50人が出席した。
佐藤克久部会長は「生産者の皆さまより不安定な天候にうまく対応し、より高品質は品物を多く出荷していただいた。販売先・市場からの高い評価や期待に応えられるよう頑張っていこう」とあいさつ。
平成29年度の販売額は5億7000万円となった。天候不順による悪影響はあったものの、前年度比本数増と、2日前集荷を全品目で実施したことなどが実績につながった。また消費地での販促活動にも積極的に取り組んでおり、前述の2日前集荷の実績と併せて、主な出荷先である株式会社フラワーオークションジャパンよりFAJオブザイヤーに選出された。
平成30年度の活動計画として、生産・販売面ではさらなる増反・増産を目指し、生産者の課題克服に取り組むこと、マーケットに合わせた作付け・商品提案を行っていく。組織面ではより活発な組織活動を目指し、これまでの専門部体制の再編や役員改選などが承認された。上野善光新部会長の下、部会員一丸となって販売額6億円を目指し取り組んでいく。
その後の研修会では「消費地に求められる花のトレンドと今後の展望」と題した講演が行われた。

17年度を総括した佐藤克久部会長

選出された新役員の皆さん
伝統料理を持ち寄り食文化を見直す/女性部上郷支部
JA鶴岡女性部上郷支部は2月24日、伝統料理を持ち寄る「第8回いただきます!」を三瀬コミュニティーセンターで開き、部員や市民など約40人が参加した。
参加者が持ち寄った昔ながらの料理を一緒に味わうことで、地元の食文化や食材の良さを再確認し、先人の知恵を学びながら交流を深めることが目的。
石塚公美上郷支部長は「プチあじ自慢大会改め、いただきますに行事名を変更して一年ぶりに開いた。地域の食文化を改めて見直し、私たちが次の世代に伝えていかなければならない」と話した。
第1部では、鶴岡市水無の斎藤伊登子さんと宮田文さんを講師に、「いももち」の作り方を学んだ。一晩浸水させたもち米をふかして餅をつき、あくで煮たジャガイモを混ぜながらこねるところを実演し、あんこを付けて試食した。
第2部では、イタドリを使った山菜料理や干し柿の白あえ、昆布煮など、約30品の家庭料理をバイキング形式で試食。参加者同士作り方を教え合いながら、各家庭の料理を味わっていた。
参加者は「昔ながらの料理の作り方を親から聞かないでしまったけど、こうやって地域で教えてもらえてありがたい。自分が作ったものを皆からおいしいと言ってもらえてうれしかった」と笑顔で話した。

イモモチの作り方を学ぶ参加者。

作り方を教え合いながら楽しく会食。
産直館全体会議で研修と今年度を統括
JA鶴岡産直課は2月21日、産直会員・関係者約140人が出席して研修と全体会議を開いた。
(公財)山形県企業振興公社の専門支援コーディネーターの桜井真理子氏が、「お客さまにとって魅力ある農産物直売所~さらなるリピーター創出のために~」と題して講演。桜井氏はお客さまが繰り返し直売所に足を運ぶ条件として、新鮮な農産物が安く、地域の特産品や珍しいものなどが購入できるなど、わざわざ行く価値があること、食材の特徴や調理法などについて気軽に質問できるなどコミュニケーションがあること、品質が良く、品目が多く選択肢が多いことなどをあげた。さらに最近の売れ筋商品の傾向として「少量サイズやカット野菜、調理がめんどうなどの理由で家での調理が敬遠されがちな郷土食や家庭料理なども需要がある」と具体的にアドバイスした。
研修後に開いた全体会議では、2017年度の事業内容や販売実績が報告された。五十嵐正谷産直館運営委員長はあいさつで「産直館も15周年を迎え、新名称を募集し7月にリニューアルオープンする。一度原点に立ち返り、販売高10億円を目指そう。次の世代に夢と希望のある農業をつないでいこう」と力強く述べた。
2017年度は、天候の影響を受け全体的に品不足だったが、全国の産直との連携による品ぞろえの強化により、売り上げと集客力のアップにつながった。白山店、駅前店、のぞみ店の3店舗合計で売上高7億7000万円となる見込みとなった。2018年度は販売高8億円を目指す。営農指導員からは、不足がちな冬野菜出荷の協力や、栽培履歴書の提出について呼び掛けられた。2018年度には品目の拡大を目的とした新品目の試作に取り組むことが報告された。

魅力ある直売所づくりについて学ぶ産直会員。
タグ :直売所 もんとあ~る
げんき部会 学習会・通常総会を開く
JA鶴岡げんき部会は20日、鶴岡市湯野浜温泉の愉快亭みやじまで学習会と第16回通常総会を開いた。関係者21人が出席した。
学習会は、大戸眞澄氏が演歌を使った健康づくりとして、歌や歌手に関するエピソードなどをギターの弾き語りで替え歌など織り交ぜながらおもしろおかしく紹介。
大戸氏は「たくましくいるためにも、なんでも見てみよう、やってみようといったやじ馬根性が必要」と伝えた。
参加者は、一緒に歌い笑いあって楽しく健康づくりを学んでいた。
総会は、2017年度の活動内容の他、18年度の活動計画では学校、市民を対象にした各種活動を通じてそば打ち・わら細工などの伝承指導を行うことや予算案、役員選任などが承認された。

大戸氏は替え歌を通じて心の健康を伝えた
ワナゲ交流会を開く/JA鶴岡年金友の会
JA鶴岡は2月20日、鶴岡市農村センターでJA鶴岡年金友の会ワナゲ交流会を開き、約140人の会員が参加した。
同交流会は、「心と健康を輪でつなぐ」を合言葉に会員相互の親睦と、健康増進に寄与することを目的に開かれており、今年で2回目。
開会式では、伊藤淳専務が「健康に留意しながら、日ごろの練習の成果を十分発揮してほしい。交流会を契機に、融和と健康増進に努めてほしい」とあいさつした。
その後26チームに分かれて一斉にプレイを開始、一人3ゲームを行った。
寒さを吹き飛ばす熱戦が繰り広げられた結果、個人戦では同市高坂の長谷川富子さんが、パーフェクトも含めて合計630点の成績で優勝。
また、チームの合計得点で競う団体戦では「田川A」チームが2年連続優勝となった。

高得点を狙う参加者

優勝した長谷川富子さん(中央)
JA鶴岡女性大学「第5回きらめきカレッジ」手作り茶わんでお茶を楽しむ
JA鶴岡は2月20日、鶴岡市農村センターで女性大学「きらめきカレッジ」第5回を開き、受講生11人が参加した。「和の心 お茶を楽しむひととき」をテーマに、茶のたて方や茶席の作法を学んだ。
裏千家の同JA五十嵐千代美理事から、長芋ときな粉を使った簡単団子の作り方や、茶のたて方などを学び、五十嵐理事がたてた薄茶をいただいた。
その後、第1回講座で作成した抹茶茶わんを使って、各自が茶をたて、緊張した表情ながら、茶や菓子をゆっくりと味わっていた。
参加者は「抹茶のたて方や作法などを学べて勉強になった。自分で作った茶わんでお茶が飲めてうれしかった」と話した。
「JAの時間」では、市民を対象に食と農への理解を深める「あぐりセミナー」や、親子で農業体験をする「あぐりスクール」などの生活文化事業について紹介した。
講座終了後には2期生の卒業式を行った。2年のカリキュラムを修了した卒業生たちは、学長の佐藤茂一組合長から修了書を受け取り、「いろいろな体験ができ、楽しくためになる時間だった」と振り返った。
佐藤茂一組合長はあいさつで「卒業おめでとう。趣味を持ってこれからの人生を楽しんでほしい。今後もぜひJA鶴岡の事業に参加してほしい」と述べた。
「きらめきカレッジ」は、管内の若い女性を対象に、2年1期の全10回でさまざまな分野の講座を仲間と楽しく学び、自分を磨くことを目的に、2015年に開校。2018年春には、4期生を募集する。

茶のたて方を学ぶ受講生。

簡単和菓子ができました。

2期生と3期生で記念写真。