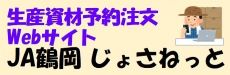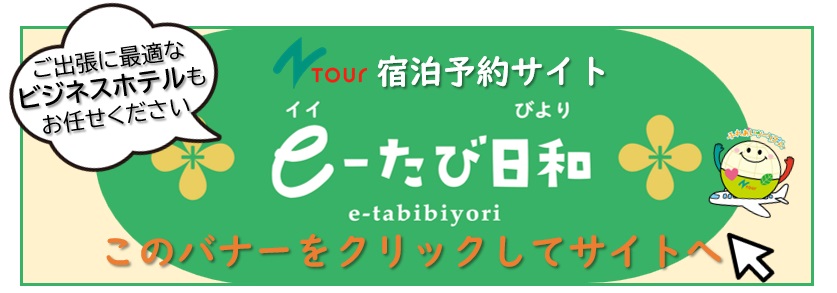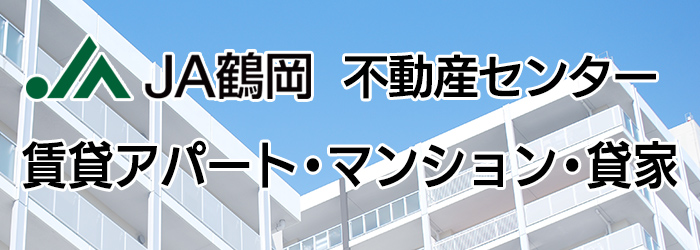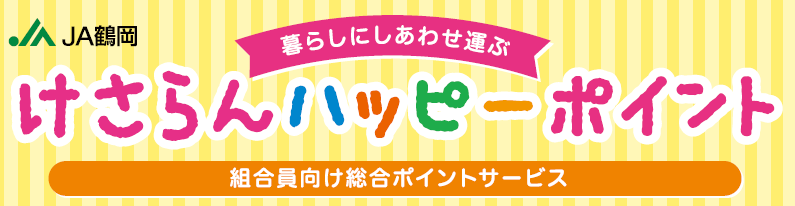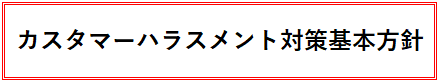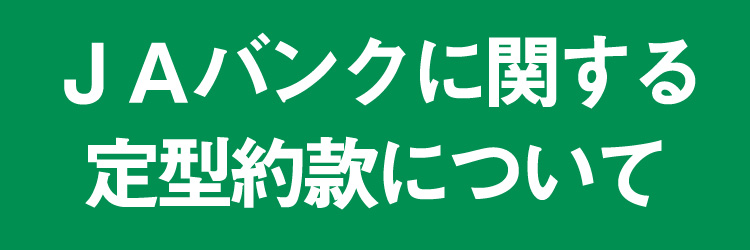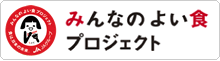きらめきカレッジでアロマリラクゼーションヨガ体験
JA鶴岡は11月26日、鶴岡市農村センターで女性大学「きらめきカレッジ」第2回を開き、受講生9人が参加した。
健康運動実践指導者で、シナプソロジーインストラクターの前田恵さんが「心と身体と向き合う時間~シナプソロジーとアロマリラクゼーションヨガ~」をテーマに指導した。
シナプソロジーは、二つのことを同時に行ったり、左右で違う動きをしたりするなど、普段慣れない動きで認知機能の改善を図る脳の活性化プログラム。参加者は、声を出して笑いながら楽しく体を動かして認知機能を高めた。
アロマの効果で心の緊張が取れて、効果的にヨガのポーズを味わうことができるアロマリラクゼーションヨガでは、ラベンダーとベルガモット、殺菌作用のあるティートゥリーをブレンドした香りに包まれながらヨガを体験。呼吸に合わせて背中を丸めたり伸ばしたりする猫のポーズなどで全身を気持ちよくほぐした。前田さんは「ヨガを日常に取り入れて心と身体の健康づくりをしてほしい」と話した。
「JAの時間」では、職員が「鶴岡の花」をテーマに、JA花き振興部会の取り組みや、花の栽培から出荷までの流れなどを紹介した。

前田さん㊨の指導でヨガのポーズをとる受講生
げんき部会がそば打ち体験
JA鶴岡げんき部会は11月25日、鶴岡市西郷農林活性化センターで会員14人が参加してそば打ち体験をした。会員が7月にそばの種をまき、収穫してひいたそば粉を使用した。
前田哲男会長は「新型コロナウイルスの影響で会食はできず残念だが、会員が育てたそばでそば打ちを楽しもう」とあいさつ。
参加者はJA鶴岡ショートステイ愛あい館の難波隆博所長の手ほどきでそばを打った。そば粉に適量の水を混ぜた後、手際よくこねた。麺棒を使って生地を均等に広げ、包丁でそばの細さに切って完成させた。
参加者の五十嵐寿美子さん(81)は「毎年楽しみにしているので開催できてよかった。みんなでおしゃべりしながらそば打ちをして楽しかった」と話した。
同部会は設立17年目で会員は23人。生涯現役を目指し、生きがいや健康づくり、農村文化伝承を通して地域と交流を続けている。

そばの生地を麺棒で広げる会員

そばを切る会員
女性フェスティバルで心休まるひとときを
JA鶴岡女性部は11月17日、鶴岡市の荘銀タクト鶴岡で「JA鶴岡女性フェスティバル」を開き、部員・関係役職員ら約140人が参加した。
渡部優子部長は「コロナ禍で思うように女性部活動も開催できない現状だが、今日は目いっぱい楽しんでほしい」とあいさつ。
宮城県仙台市を中心に、南米の楽器であるバンドネオンとアルパの異色デュオ「Apolonita(アポロニータ)」として演奏活動を行っている渡辺公章さんと美和さん夫妻を招き、コンサートを開いた。
南米伝承曲の「コンドルは飛んで行く」や、久石譲さんの「もののけ姫」、加山雄三さんの「君といつまでも」などを披露。JA女性の歌「明日 輝くために」を特別に演奏いただき、参加者は口ずさみながらバンドネオンとアルパの音色を楽しんだ。
参加者は「初めて見る楽器から奏でられるきれいな音色に癒された」「心和むメロディーで至福のひとときを過ごせた」と話した。
例年は、女性部員と組合員を対象に、女性部の重点目標である「食と農を守る活動」の地産地消運動を軸とした女性部活動の集大成と、部員同士の交流を目的に1日がかりで行っていたが、本年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、内容を見直しコンサートとお楽しみ抽選会のみ実施。参加者はマスクを着用の上、検温、手指消毒の感染防止対策を講じ、お互いの間隔を取りながら楽しんだ。

会場はバンドネオンとアルパの心地よい音色に包まれました。

お楽しみ抽選会では出演者のCDなど豪華景品が当たりました!
東京の児童に稲作授業 米産地の思い知って
JA鶴岡青年部は11月13日、東京都江戸川区立第五葛西小学校の5年生を対象にした食農授業を鶴岡市のJA本所とオンラインで結んで行った。
例年は、6月に同市と友好都市の江戸川区の小学校約15校に出向いて、稲作の特別授業を行っていたが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン授業として企画。市の東京事務所の協力で実現した。
青年部員と児童は、JA本所のパソコンと小学校の電子黒板の画面やテレビ電話を通じて授業を行った。児童は、総合学習や社会科の授業で学んだ米について発表した後、青年部員から農家になったきっかけや米作りでの苦労話、おいしいご飯の炊き方などについて質問しながら話を聞いた。
青年部の佐藤大樹委員長は「オンライン授業という形にはなったが、東京の児童に産地の思いを伝えることができた。今回の経験を基に今後の事業につなげていきたい」と話した。

リモートで米作りについて話を聞く児童
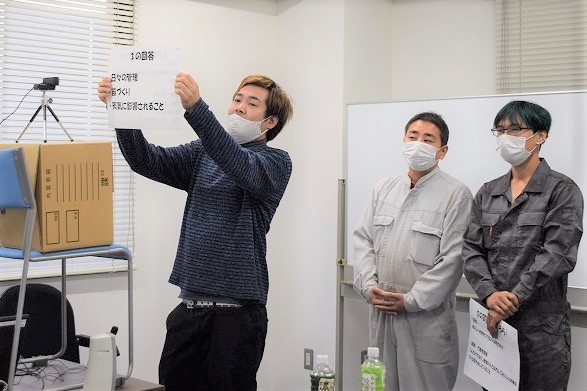
児童からの質問に答える青年部員
ストック目揃い会を開く
JA鶴岡のストック専門部は11月9日、鶴岡市のJA北部集出荷場でストック目揃い会を開いた。生産者と関係職員の約30人が参加して出荷規格や出荷調整などを確認した。
同専門部では部員37人がストックやスプレーストックを栽培し合せて約70万本の出荷を予定している。販売額は約5600万円を見込む。
池田賢成専門部長はサンプルを見せながら等・階級ごとの出荷規格基準や箱詰めの注意点などを説明した。また、今後の管理について「今年は生育が遅れているので、ハウス内の適温を確保するためハウスの開け閉めをお願いする」と呼び掛けた。今年は9月の猛烈な残暑が花芽分化に影響し生育が遅れている。
10月下旬に出荷がスタートし、11月下旬から12月上旬をピークに翌年2月頃まで続く見通しで、主に関東市場へ出荷される。
.jpg)
等・階級ごとの出荷規格基準を説明する池田賢成専門部長㊨
鶴岡市にカーブミラーを寄贈
交通事故防止に役立ててもらおうと、JA鶴岡、JA庄内たがわ、JA共済連山形は11月9日、鶴岡市にカーブミラー21基を寄贈した。
地域貢献活動の一環として昭和48年から寄贈し、寄贈数は延べ1452基となった。
JA鶴岡の佐藤茂一組合長とJA庄内たがわの菅原勝専務が市役所を訪れ、皆川治市長に目録とレプリカを手渡した。
皆川市長は「毎年継続して寄贈頂き感謝する。各自治会より新規設置や老朽化による更新などの要望を多く頂いているので、有効に活用していく」と話した。
JA共済連山形は、7月に発生した山形県豪雨災害での共済金の支払い状況や、アンパンマン交通安全キャラバンなどJA共済が取り組む地域貢献活動を報告した。

皆川市長㊥にレプリカを手渡す佐藤組合長㊧と菅原専務
JA鶴岡ローンキャンペーン2020-2021
『JA鶴岡ローンキャンペーン2020-2021』を実施中!

『JAマイカーローン』はお客さまの様々なカーライフを応援
『JAマイカーローン』は、自家用車・バイクの購入はもちろんのこと、カー用品購入・車検・修理・運転免許取得などにもご利用いただけます。
また、金利が高い他社マイカーローンのお借換にもご利用可能であり、カーライフに関する様々な用途にご利用いただけます。
『JA教育ローン』は、お子様のひとり暮らしの費用もOK
『JA教育ローン』は、高校・高専・短大・大学・専修学校等の入学前に必要な入学金や授業料などの学費はもちろんのこと、在学中のお子様の授業料にご利用いただくことも可能です。
さらに、お子様がひとり暮らしを始める際にかかる、アパート代や下宿代などにもご利用可能であり、教育に関する全ての資金をサポートいたします。
※お借入れ・金利引き下げ条件など詳しくはこちらをご確認ください
オータムフェア2020 家電や寝具特価で販売
JA鶴岡は10月31日、11月1日の両日、鶴岡市のJA大泉支所でオータムフェア2020を開いた。暖房機や有機ELテレビなどの各種家電製品、ガス器具、仏具、寝具などの生活関連用品やオーダーメイドの紳士服などを販売。JAすまいるプラザでは旅行の相談や葬儀の事前相談を行った。
2日間で308戸の組合員と家族が訪れた。
生活課の工藤妙課長は「これから迎える冬を快適に過ごすための生活用品を取り揃えた。コロナ禍の中、多くの方にご来場いただきありがたい」と述べた。
給油所JASS-PORT鶴岡のガソリン・軽油の大特価と粗品進呈も企画。その他、菓子工房けさらんハウス「ママの会」がきんつま焼きの販売などでフェアを盛り上げた。

お薦め製品の機能や特徴を説明するJA職員㊨

仏壇・仏具を展示した会場
大きく成長し下牧 月山高原牧場から牛舎へ
鶴岡市羽黒地区にある庄内広域育成牧場(月山高原牧場)で10月30日、今シーズンの放牧が終了し、夏場を過ごした牛を畜産農家に戻す下牧作業が行われた。
同牧場には、5月に鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町の2市2町の畜産農家43戸から約170頭が運び込まれ、JA鶴岡管内の畜産農家5戸から38頭が入牧。月山山麓の標高約350㍍にあるので夏でも涼しく、約100㌶もの広大な牧草地での放牧は、産後の体力回復や受胎に向けた体づくり、農家の負担軽減が目的。
放牧期限のこの日まで残っていた牛たちは、1頭ずつ体重と体高を測定された後、トラックで各農家の牛舎に運ばれた。
市内で和牛繁殖経営を営む佐藤正さん(西京田)は「牛たちの健康増進と農家の負担軽減につながる。これから元気な子牛を産んでほしい」と話す。

牛をひく佐藤さん

牛追いの様子
ラ・フランス目揃い会を開く
JA鶴岡の西洋梨専門部は10月30日、鶴岡市のJA北部集出荷場で秋の味覚として人気の西洋梨「ラ・フランス」目揃い会を開いた。
同専門部では、部員10名が栽培。今年は順調に生育し台風などの被害もなく収穫を迎えた。出荷量は例年並みで約10㌧を見込む。
JA園芸指導係は形状やスレ傷など等級ごとの基準をサンプルを見せながら説明し、「今年は輪紋病発生が見受けられるため選果選別をしっかりして、多くの出荷をお願いしたい」と呼び掛けた。
出荷は同日に開始し11月下旬まで続き、全国へ出荷される。

サンプルで出荷規格を確認する生産者